ポラニーによれば、近代以前の社会において、経済活動は常に共同体のルールや社会的関係の中に「埋め込まれ」、それに従属するものだった。
しかし19世紀以降、本来は市場で売買されるために生産されたのではない「労働、土地、貨幣」までもが商品(擬制商品)と見なされ、経済が社会から分離してしまった。
市場原理という「悪魔のひき臼」が社会をすり潰していくこのプロセスこそが、ファシズムや世界大戦といった20世紀の悲劇を招いた、とポラニーは論じる。
ドラッカーとポラニーに共通するのは、人間や社会を土台から切り離し、経済を自己目的化してしまうシステムの危うさへの鋭い洞察である。
そしてマッテイの『緊縮資本主義』は、この思想的警鐘が、いかに「緊縮」という名の現実の政策として世界を覆っていったかを生々しく暴き出した、いわば『大転換』の現代的実践報告とも言えるだろう。
エリートの歪んだ使命感と高揚感
本書の最大の魅力は、マクロ経済データによる実証にとどまらない、その多層的な分析にある。
その真骨頂は、政策担当者が残した覚書や書簡、国際会議の議事録といった膨大な一次資料を渉猟し、その行間から彼らの生の声を蒸留してみせる、卓越した筆致だ。
そこからは、彼らが労働者大衆を「理解不能な怪物」として恐れ、その怪物を退治することにエリートとしての使命感と高揚感を抱いていた様が生々しく伝わってくる。
とりわけ衝撃的なのは、民主主義の優等生であったイギリスと、ファシズムの後進国イタリアが、「緊縮」という一点において完全に目的を共有し、固く手を結んでいたという事実だ。ここが本書の第二のクライマックスである。




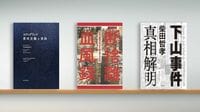


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら