そこに集った各国の経済学者や財務官僚、銀行家たち(本書では「テクノクラート」と総称される)は、資本主義の秩序を再建するための、壮大な「反革命」の司令塔となった。
彼らは、政治家とは一線を画す「中立的な専門家」として客観性と科学性を装いながら、その実、大衆を無力化し、資本主義の秩序に再び従わせるための政策パッケージを練り上げていった。
均衡財政、公的支出の削減、間接税の強化、金融引き締め――。これらの政策が、いかに労働者階級の交渉力を奪い、生活基盤を破壊するためにデザインされたかが、克明に論じられる。
驚くべきことに、この時かたちづくられた緊縮策の基本思想と手法は、100年後の現代に至るまでほとんど変わらずに生き続けている。
これこそが、私たちを縛り付ける「呪縛」の起源なのである。
ドラッカーとポラニーの視点
本書が描き出す「人間不在の経済学」の危険性をより深く理解するために、2人の思想家の補助線を引くことは有効だろう。
一人は、私が専門とする経営学者のピーター・ドラッカーである。
彼の生涯は、本書が分析対象とする時代と完全に重なる。ナチズムの台頭をウィーンとフランクフルトで目の当たりにしたドラッカーは、人間を単なる手段や抽象的な「経済人」として捉える近代的な思想が、いかに容易に全体主義へと至るかを痛感していた。
彼がその生涯を通じて警鐘を鳴らし続けた「人間なき知識」と「全体主義」の親和性は、まさにマッテイが告発するテクノクラート支配の思想と軌を一にする。
経済モデルの美しさや数式の整合性のために、生身の人間の尊厳や暮らし、社会の安定が犠牲にされる。ドラッカーは自らを「社会生態学者」と呼び、経済とはあくまで人間社会という生態系の一部であり、社会全体の健全性に貢献して初めて意味を持つと考えた。
この視点は、緊縮策の非人間性を告発する本書の議論と強く共振する。
もう一人は、ドラッカーとも親交のあった思想家カール・ポラニーだ。
彼の不朽の名著『大転換』は、自己調整的に動く市場経済というユートピア思想が、いかに人間社会の基盤を破壊するかを精密に描き出した。




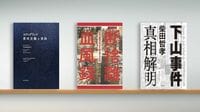


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら