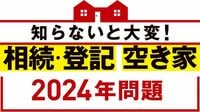「私には家庭があるから」。親の介護を押しつけるが相続財産は請求、兄弟姉妹で起こる争いの「対策」は?
両親の遺産を「相続する」ということと、「今後一切、連絡は弁護士である代理人を通してほしい」という内容だった。
きょうだいは、被相続人の子どもとしての「法定相続分」を受け取る権利を主張したが、姉小路さんは父親の老人ホームの入居費、母が必要とする日用品などを計数百万円で立て替えていた。
その介護にかかった費用の扱いと遺産の分割をめぐり、きょうだいが争うことになったのだ。
「寄与」の主張に壁
民法では、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献(介護、事業の手伝いなど)をした法定相続人は、他の相続人よりも多くの相続分を受け取ることができると定め、これを「寄与分」という(民法904条の2)。
さらに2018年に改正された民法では「特別寄与料制度」が設けられ(民法1050条)、法定相続人ではない長男の妻などの親族が介護などで特別の寄与をした場合に金銭を請求できるようになった。
遺産相続における「寄与分」「特別寄与料」は、介護で苦労をした人に報いる手段となるはずだが、実際に認められた例は少ないようだ。
遺産相続などにも詳しい「稲葉セントラル法律事務所」(東京・大田区)の稲葉治久弁護士は、「残念ながら、介護をした相続人が十分に報われるような制度ではない」と指摘する。
たとえば、相続人の「寄与分」は、デイサービスなどの公的介護保険サービスを使っている場合は認められず、寝たきりの家族を在宅で24時間見ていたり、自分のお金を持ち出して介護をしたりしている場合に裁判所が認めるが、そのハードルは高いという。