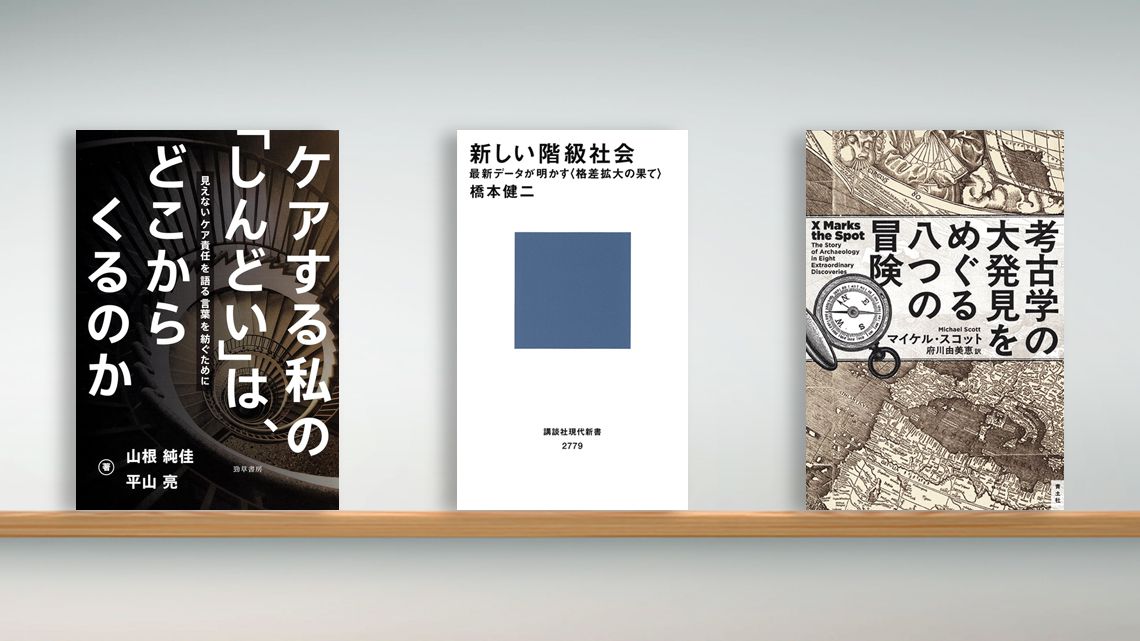
[Book Review 今週のラインナップ]
・『ケアする私の「しんどい」は、どこからくるのか 見えないケア責任を語る言葉を紡ぐために』
・『新しい階級社会 最新データが明かす〈格差拡大の果て〉』
・『考古学の大発見をめぐる八つの冒険』
評者・医療社会学者 渡部沙織
人は生まれてから天寿をまっとうするまで、必ず誰かの手助けや見守りなどのケアを必要とする。産業化以降、子どもや高齢者のケアを担ってきたのは主に家庭内の女性だ。労働はモノを生産する市場にのみ存在すると捉えてきた古典的経済思想の下で、育児や介護は「女性なら誰でもできる労働」と捉えられがちだ。
名もなきケア労働のプレッシャー 古い規範をどう乗り越えるか
英国の社会学者ジェニファー・メイソンは現代のケア労働をSentient Activity(SA)と呼んでおり、本書の著者らはこれを「感知し考える活動」と訳している。ケアはそれを行う者にとって、精神と身体の能動的な活動だ。依存的な存在に対して、よりよい状態を実現する責任を引き受け、考えることを伴う。
「他者のよりよいあり方の実現」という重圧に悩み葛藤する現代の女性や男性は、どのような責任や規範の論理にからめ捕られているのか。本書はそれをSAを足がかりに分析していく。




































無料会員登録はこちら
ログインはこちら