なぜシンガポールは国の中央に「空虚な穴」を作ったのか 資源なき都市国家が貫く意外な生存戦略と、「価格に応じて生き方が決まる」日本の閉塞感
その戦略の一環として、多国籍企業の誘致やグローバル資本の流入に積極的であることは明らかだ。
つまりシンガポールという国は自らを「世界のフローの中継点」として設計している。人、モノ、金、情報、それらを常に流動させ、その中心にあるのは空虚な穴だけが残されている。その姿はジュエルの中央に開いた穴に、水が滝のように流れ込む構造と重なって見えたのだ。
ご存知のとおり、水も金も流れを止めれば濁ってしまう。シンガポールという都市国家は、その流れを止めないことで命脈を保ち続けているのだろう。
そして奇妙なことにそんな国の紀伊國屋書店で、僕の著書『武器としての土着思考』が棚に差さっていたのを見つけた。人とモノと金が絶え間なく流れ込むその都市で、「土着」を語る本が置かれていたのだ。しかし僕にはそれが単なる偶然とは思えなかった。
シンガポールに見た「土着」という生存戦略
僕の言う「土着」は、一般的に使われる「もともとそこに存在していた」とか「原住の」といった意味とは異なる。
それはむしろ、例えば資本とケアという、しばしば対立的に語られる2つの原理を行ったり来たりしながら折り合いをつけ、自分にとってちょうどいいバランスを見つけ出す、そんな動詞的な営みを指している。
つまり「土着する」とは何かに帰属することではなく、対立を抱えながら、それでも共に生きていく術を見つけるプロセスのことなのだ。
それは資本とケアに限らず、頭と身体、都市と自然、人間と動物など、対立的に語られがちなあらゆる関係に当てはまる。重要なのはそれらを単純な二項対立に押し込めず、あくまで関係のなかにある共通点や緊張感を見極め、揺れ動きながら生き続けることだと思っている。
そう考えるとシンガポールという都市国家は、意外にも「土着する」ことを体現している一例なのかもしれない。
資源も土地も乏しく、国土も狭いなかで、資本主義を極限まで推し進めながらも、国家の生存や国民の生活という「ケア」の論理とも向き合っているともいうことができるからだ。
絶え間ない流れのなかで形を定めず在り続ける姿は、まるでジュエルの中央に開いた穴へと水が途切れることなく流れ込んでいく構造そのものではないか。空っぽの中心を抱えながらも全体としては秩序を保っている。それこそが僕の言う「土着」の状態に近いのではないかと思ったのだ。
流れが正しいものであるならば、それを止めないこと。変化のなかでこそ安定を見出すこと。もしかすると紀伊國屋書店シンガポール店の書店員さんは、その感覚を無意識のうちに掴んでいたのかもしれない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら




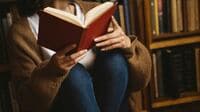


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら