なぜシンガポールは国の中央に「空虚な穴」を作ったのか 資源なき都市国家が貫く意外な生存戦略と、「価格に応じて生き方が決まる」日本の閉塞感
そんなシンガポールへは関西国際空港(関空)からおよそ5時間のフライトだった。僕はLCCのPeachを使って行ったこともあり、チケットは往復で4万円もしなかった。
コストパフォーマンスとしては十分だったのだが、出発地である関空第二ターミナルのあまりに貧相な佇まいには心底がっかりしてしまった。プレハブのような建物、狭くて殺風景な待合スペース、ほとんど選択肢のない売店。それらは単なる設備の乏しさというより「LCCならこれで十分でしょ」という、どこか見下したような経済観念の表れに思えた。
お金を払っていないのだからサービスや空間の質も落ちて当然だという、日本社会に広く浸透した価値観が透けて見えたのだ。まるで「価格に応じて生き方まで条件づけられる」ような感覚に、僕は心底落胆してしまった。
なぜシンガポールは「空虚な穴」を作ったのか
一方、シンガポールのチャンギ国際空港は第四ターミナルまで備えながら、どこも一定水準以上の快適さが保たれていたし、利用する航空会社のグレードによって露骨に空間の質が上下するような印象はなかった(なにせ帰りの飛行機を待つために、6時間以上空港に滞在していたのだから間違いない)。
つまり公共的な場において、「安い=劣る」という発想に基づいた線引きを極力排しているように感じられたのだ。その差は単なる空港設備の話にとどまらず、社会全体の人間観や尊厳に対する態度の違いを映し出しているように感じてしまった。
さらに、空港には「ジュエル(Jewel)」という巨大なショッピングモールが隣接している。中心には円形の吹き抜けがあり、そこに大量の水が上から流れ込んでいる。要するにショッピングモールの中央に、巨大な人工の滝があるのだ。なぜだか僕はこの光景こそがシンガポールという国のあり方を象徴しているように思えた。
シンガポールは国土が極端に狭く、農業に適した土地も乏しい。食料自給率は10%を下回り、ほとんどすべてを輸入に頼っている。そんな小国が生き残るために選んだのは国策としての徹底した資本主義路線だった。
70年代以降、製造業を核に経済を発展させ、80年代からは金融資本主義へとシフトしていった。政治的には長年、人民行動党(PAP)によるほぼ一党独裁状態が続いており、民主主義としては健全とは言いがたいが、それもまた生存戦略として考えることができるだろう。




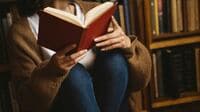


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら