なぜシンガポールは国の中央に「空虚な穴」を作ったのか 資源なき都市国家が貫く意外な生存戦略と、「価格に応じて生き方が決まる」日本の閉塞感
僕が10代を過ごした90年代後半から2000年代初頭は、「自分探し」のような言葉がやけに響く時代だった。バブルが崩壊し「失われた10年」が始まり、どこかで閉塞感を感じながらもまだインターネットはそれほど普及していなかったから、海外は未知で眩しかった。
だからこそ「ここではない、どこか」に希望を託す想像力が、音楽や雑誌やテレビの向こう側に確かに漂っていた気がする。僕もまたその空気のなかで育ち、自分にとっての理想的な「どこか」を探していた。僕の西洋への憧れは、そうした時代の空気に支えられていた。
さらに僕は文化遺産に関心があったから、直感的にシンガポールとは結び付いていなかったのである。シンガポールといえばガムを食べながら歩いていると罰金が科されるとか、あるいは白亜のライオンと魚が合わさったような像の口から水が出ているあの噴水公園などを、社会科の資料集やテレビで目にしたことがあっただけだったのだ。
【2025年8月25日9時14分追記】 初出時、シンガポールについて「ルックイースト政策という日本にならって経済成長を進めたこと」と記載していましたが、正しくはマレーシアの政策でしたので、この部分を削除します。
「移民の街」であり「交易の中継地」
案の定シンガポールの観光地について調べてみると、古代遺跡や宗教的建造物といった文化遺産はほとんど存在しなかった。むしろ歴史の中心は、ヨーロッパ諸国が世界中に船を出し始めた大航海時代以降に始まる。さらにいえばその後進国だったイギリスがこの地を戦略的拠点と定めてからの歴史こそが、現在のシンガポールの出発点となっている。イギリスは香港やジブラルタル、マルタ、ケープタウンなど、要衝の港に拠点を構え、海上帝国のネットワークを築いたが、その一環として1819年、東インド会社のスタンフォード・ラッフルズがシンガポールに上陸し、ジョホール王国との条約を経て自由港として整備したのが近代史のはじまりだった。
そうした背景のもと、シンガポールは東アジアとインド洋世界を結ぶ交易と軍事の中継地として急速に発展していった。中華系の華人、インド系のタミル人、そして地元に近いマレー系の人々がこの地に移り住み、社会が形成されていったのである。つまりシンガポールは固有の民族文化が歴史的に育まれてきた土地というよりも、外から移り住んできた多様な人々が集まって形成された「移民の街」であり、その混成性こそがこの国の特徴の一つをなしていたのだ。




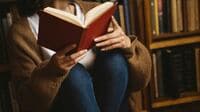


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら