もちろん、魚においても例は見られるが、サケと違って展示物の腹をザクザク切り裂くわけにはいかないので、主に「腹を刺激して卵を絞り出す」という方法で行われる。
先ほどの、サケのオスと同じ方法だね。この方法により、初めて繁殖に成功した魚もいる。
ちなみに、この例外はチョウザメで、腹を裂いて卵を取り出しても、丁寧に縫い合わせれば死ぬことはないらしい。これは繁殖に限らず、キャビア(チョウザメの卵)を取り出すときにも使われる。世界三大珍味の1つであるキャビアは、親を生かしていれば何度も採れるのだ。
それよりも人工授精で有名なのが、哺乳類や鳥類である。水族館においては、イルカやアシカ、ペンギン、あとは一部のサメなどが該当するのだが、これらは受精を体内で行う生き物だ。
人間の代理出産を考えれば分かるだろうが、このような生き物は、体外で受精させた卵をそのまま放っておいては死んでしまうので、もうひと工夫いる。すなわち、受精卵をメスの体内に戻してやる作業が必要なのだ。
無事に戻せれば、あとは自然繁殖と同じように親に育てさせればいい。口で言うのは簡単だが、これはかなり難しい工程を伴う。
水族館では海獣医師などの立会いの下で行われ、しかも常に成功するとは限らない。
だが、これが成功すれば、水族館では繁殖の難しい種、もしくは自然繁殖の難しい個体でも子孫を残させることができる。まさに、生き物を愛する人間の叡智なのだ。
ここまで見てきたように、繁殖は何も自然に行われるものに限らない。人工授精も立派な繁殖の試みである。
*なお、川に上がる頃のサケのイクラは皮がパッツパツに張っており、硬くて味が落ちるとされる。本当に美味しいのは、川に上る前に海で捕獲したサケのイクラである。ま、どうでもいいマメ知識だけどね(笑)。

ラッコやペンギンの家系図
第1章で語ったラッコほどではないものの、個体数の少ない動物ではその“家系図”を書くことができる。代表例として、シャチを見ていこう。
実は、日本の水族館で今飼育されているシャチはすべて、ある夫婦の系譜である。それが、シャチのショーで有名な鴨川シーワールド(千葉県)で、1988年から飼育されていた「ビンゴ」(オス)と「ステラ」(メス)である。

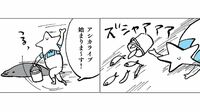





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら