迫る「2025年の崖」 ITプロジェクトが失敗する必然。BCG幹部が語る「基幹システム」刷新のポイント
――ユーザー側の企業には、ITシステムに対する深い理解と責任が必要となります。
ベンダーに丸投げせず、自社でプロジェクトを管理できる人材と知識が必要だ。ベンダーは基本的に自社に責任が及ばないよう行動するため、発注者であるユーザー側が責任を持ち、プロジェクトをコントロールしなければならない。企業の経営層は、IT業界特有の用語の不統一や要件定義と基本設計の曖昧な線引きに匙を投げてはならない。
日本企業では、システムの異常処理への過剰な対応や現場の使い勝手を重視しすぎるあまり、プロジェクトの中身が複雑化しやすい傾向にある。「スパゲッティ化」と呼ばれるシステムの複雑な状況がIT投資の費用対効果を見えにくくしている。
ただ企業は仮に投資に失敗しても、それを隠さずオープンにし、ベンダーも巻き込みながら、軌道修正できる環境を作ることが重要だ。手遅れになる前に、勇気を持ってプロジェクトを止める決断もときには必要となる。
コンサル任せにしなかった柳井会長
――既存の業務プロセスをシステムに合わせて標準化する「フィット・トゥ・スタンダード」が、逆にシステムの複雑化を招く皮肉的な状況も生まれています。
企業は現場のプロセスにシステムを合わせるのではなく、意思決定に必要な情報がシステム全体で統一されたデータ構造で取得・管理できることに注力すべきだ。これにより、不必要な情報の蓄積を防ぎ、システムをシンプルに保つことができる。
たとえばファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、店舗運営からサプライチェーン、物流までを自ら経験し、ITシステムの重要性や限界を深く理解している。
すべての情報を網羅的に見ようとするのではなく、意思決定のポイントを明確にしたことで、システムをシンプルに保ち、迅速な意思決定を可能にした。経営者自身がシステムを理解していたからこそ、コンサルの言うことを丸呑みせず、不要な機能導入を避けることができた。



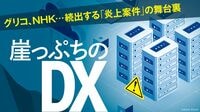



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら