
背景に家父長制の残滓
――国会では28年ぶりに選択的夫婦別姓を導入する法案が審議されたものの、結局は採決まで至りませんでした。
なぜ審議が滞っているのか不思議です。名前が変わるのは人格権の問題で、女性の権利が侵害されているということです。旧姓で働き続けている女性がたくさんいて、不都合なことが起きているのだから、通称使用の拡大でごまかしてはいけないと思います。
保守系政治団体などが、選択的夫婦別姓が導入されれば古い家族制度が壊れると言って反対していますが、なぜそこまで固執しているのか、こだわりの正体が見えません。その主張の背景には、強固な家父長制の維持があります。でも、家族の形態は今、崩れつつあります。
――夫婦別姓に対するご自身の関心の契機は。
自分が結婚したときです。50年ほど前のことで、当然のように夫の姓に変えることになりましたが、夫に「(本名の)あなたはいなくなった」と言われて、すごく嫌な気持ちになったのを覚えています。完全に別の家の人間になったように扱われることも嫌でした。
私の旧姓も、私の母が譲ったからこその姓です。そうやって女たちが譲ってきたのだから、不快だけれども仕方がないのかなという感覚もありました。でも、夫婦同姓は近代に作られた戸籍制度に由来しています。根は家父長制です。

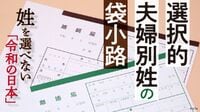































無料会員登録はこちら
ログインはこちら