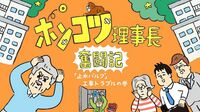日本のワイン市場、底堅い成長が続き、「質」の改善も進む

--フランス国内での消費の落ち込みに対して、業界は危機感を抱いていないのですか。
「危機」とはいえないと思います。フランスはワインの輸出大国でもあるからです。国内でも落ち込んだとはいえ、今日でも1人当たり、1週間に1本は消費しています。イタリアやスペインの生産業者にとっても自国での消費の伸び悩みは大きな問題ではありません。ドイツもそうです。ワインの輸入が増えていますが、同時に輸出も増えています。
--日本でも「アルコール離れ」が進んでおり、ビール風味のノンアルコール飲料などの需要が拡大しています。そうした中でも、ワイン市場にはまだ、潜在的な拡大の余地が残されているのでしょうか。
フランスにもノンアルコール飲料のマーケットは存在していますが、ワインの市場がなくなったわけではありません。日本でもワイン市場は2011年に対して15年には2~3%の成長は見込めるでしょう。つまり、年率で1%前後の底堅い成長が可能ということです。
日本でワインといえば、かつてはとても高い飲み物でした。しかし、今は品質や値段の異なるさまざまな種類のものが市場に供給されています。値頃感のある製品もふんだんにあります。
日本の流通業者たちがワインに関する知識などを積極的に吸収した結果、消費者側の選択の幅が広がった面もあります。日本の女性がワインをたしなむようになったのは20年ほど前からでしょうか。
最初は単に「ワイン」というお酒を口にしたいだけだったのでしょう。ところが、その後、情報入手のため書物などに目を通したり、講習会に出席して試飲をしたりする女性が増えました。