会話が苦手なビジネスパーソンを救う黄金法則。重要なのは、会話の“目的をどこに置くか”
マインド面では、先入観を捨てることが大切だ。「相手が期待しているのはこれだ」という思い込みはたいてい間違っており、話をしながら修正する必要がある。オープンマインドを心がけ、相手の言葉を素直に受け取るのだ。
感情的になると損失も
頭のいい人は話す前に何を考え、心がけているのか。1つは、感情的にならず冷静さを保つことだ。英サセックス大学教授の心理学者、スチュアート・サザーランド氏は「怒りや恐怖など強い感情にとらわれると、愚かな行動に走りやすい」と述べる。怒っているときの判断は間違っていることが多く、キレること、感情的になることは大きな損失を招きかねない。
誰しも感情的になることはあるが、それをコントロールし、冷静になって考えるほうが得策だ。相手の言葉にすぐ反応するのではなく、かつ自分の発言で相手がどう反応するか、いくつかのシナリオを考え比較検討してから言葉を口にすることが望ましい。
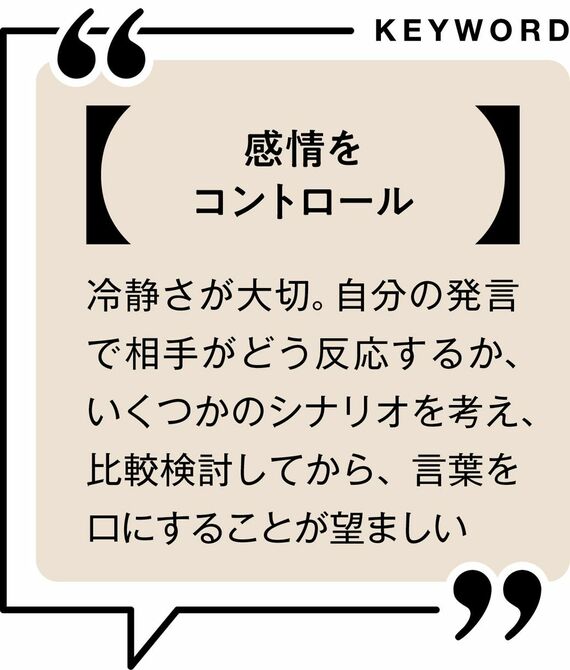
頭のよさは他人が決めるということも自覚すべきだ。知性を数字や物差しで測るのは前時代的であり、現代では人間関係の中で生まれると考えられる。学生時代は偏差値というわかりやすい指標があったが、社会に出ると高学歴=頭がよいと見なさなくなる。
賢い人に映るかどうかという評価も人により異なり、論理的に話したとしても内容が伴わないと、賢いと思われないばかりか「あの人の言うことはどこか足りない……」との烙印を押されかねない。
重要なのは「刺さる話をする」「着眼点が鋭い」「生きる力をもらった」と思われることだが、頭のよさに対する評価は人それぞれだとわかったうえで、相手によって言葉の差し出し方を変えられることが、本質的に賢いと思われる可能性が高い。
人はちゃんと考えてくれる人を信頼する。例えば、相手から助言を求められたとして、さらっとアドバイスを述べると優秀と思われるかもしれないが、継続的な関係構築に至るとは限らない。
コンサルティング会社のコミュニケーションはその点が洗練されており、必ず相手に考えさせたり、話をさせたりするような言葉を投げかける。というのも、「一緒に考えましょう」といったことにしか相手はなかなか取り組まないからだ。いくらすばらしい提案であっても、相手が関与しないと行動変容につながらない。「考えてくれている」という信頼感こそ、実効性のある策になる。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら