東京メトロ南北線、首都圏「ワンマン運転」の未来 先進技術を駆使して導入、運転士の苦労は?
東京メトロでは、列車の運行形態以外にも、設備保全業務の見直し、「状態基準保全」(CBM:Condition Based Maintenance)に向けた取り組みの検討を行っている。データが示す車両の状態に応じて、検査や機器更新を実施するメンテナンス方式、つまり、機器や設備の状態により、必要と判断された場合に適切なメンテナンスを行い、保全コストを削減できるという「次世代メンテナンス」を考えているという。また、自動運転(GoA2.5)に向けた取り組みの検討も行っている。国内において、これらの省力化・効率化が課題になっているのは、どこの鉄道事業者も同じであろう。
生産年齢人口の減少に伴う人手不足を見据え、早くからさまざまな取り組みを行ってきた東京メトロ。その先進的なシステムは、見本にすべき公共交通機関の姿だと感じる。
駅の無人化の可能性は?
首都圏ではワンマン運転の路線が拡大され、さらに一部のJRの駅などでは、時間帯によって無人化が行われている。また、西武鉄道でも3月25日以降は順次、拝島線、国分寺線、新宿線、池袋線、狭山線の11の駅で、無人化が行われている。大手私鉄路線でも無人駅化が進み、この上にワンマン運転も行われると、トラブルが生じた際に、駅に着いても駅員がいないということにもなる。運転士の負担や、利用者の不安はどこまで拭い切れるのであろうか。一部時間帯も含めて駅が無人化される可能性について、東京メトロに聞いたところ、現時点で「当社駅の無人化の予定はございません」ということだった。
安全・安心を作り出すのは人の目であると、私はつねに思っている。それが難しくなる環境で、鉄道を含む公共交通機関の安全性を保つのは、大きな課題である。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら











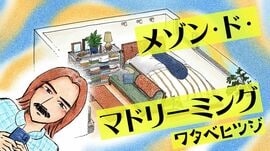




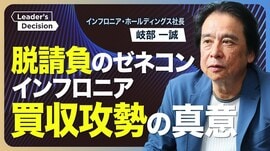




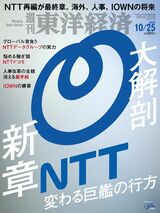









無料会員登録はこちら
ログインはこちら