東京メトロ南北線、首都圏「ワンマン運転」の未来 先進技術を駆使して導入、運転士の苦労は?
しかし、6両〜10両編成を運転士1人で預かるため、万が一、車内トラブルなどの発生や緊急事態の場合、どの程度まで対処できるかが、少々不安である。朝・夕のラッシュ時間帯などは乗客でスシ詰め状態にもなるわけで、「車掌がいない」状態になるのは、この世知辛いご時世では特に心配になる。
首都圏の普通鉄道において先進的にATOによる自動運転・ワンマン運転を実施したのは、東京メトロ(旧営団地下鉄)初のATO導入となった南北線である。1991年11月29日に、駒込―赤羽岩淵間の6.3kmが部分開業し、当初から自動運転によるワンマン運転が開始された。4両編成の短い編成ではあったが、利用者側も特に混乱もなく、2000年の全線開業以降も大きなトラブルは発生していない。
地下鉄という他の交通とは隔離された空間を走行するとはいえ、安全性の維持と乗務員への負担軽減のために、当初普通鉄道としては、初の採用となったホームドアを設置し、安全監視装置の整備、前述したATO装置の採用など30年以上も前から実施している。
なぜ南北線で始めたのか
南北線のワンマン運転の安全性はどのように保たれているのか。東京メトロに聞いてみた。
まず、南北線がワンマン運転を始めた経緯について尋ねると以下の回答があった。
「南北線については採算性を考慮しながら、21世紀を目指す便利で快適な魅力ある地下鉄とすること、および合理的な経営を維持するため、新しい視点に立った建設と運営をすることとし、ワンマン運転を導入した」
つまり、90年代初頭から将来の人手不足を念頭に対策を行い、経験を積んできたというわけだ。昨今のホームドアや自動運転の整備は、当時の方針から培ってきたと言っても過言ではないだろう。











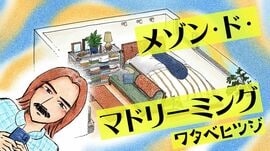




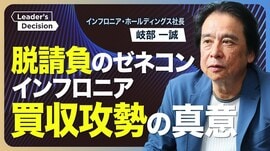




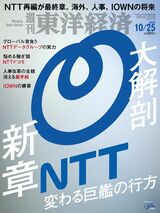









無料会員登録はこちら
ログインはこちら