子どもには「悪い子だから取り上げる」といったアプローチではなく、大人もみな誘惑に負けないよう努力していることを伝えましょう。子どもの意志を尊重して合意の上、守ることが可能なルールをつくることが大切です。
目標をブレイクダウンし、スモールステップで「やったー、できた!」の成功体験を、できたことをほめて習慣化していきましょう。少しずつステップアップして、ゲームのように自信、自己肯定感の成長を楽しめると、最高です。
うまくいかないときに、計画を修正して前向きな気持ちを維持するように心がけましょう。壁にぶつかったときに支えとなるのが、自分を信じる力です。日頃から遊びや生活の中で自己肯定感を育むことが重要です。
大人のサポートも必要
この3つの習慣が身につくまで、特に低学年のうちは大人のサポートも必要です。特に③内省的思考を育むためには、言語の発達、語彙力の発達が欠かせません。
思いどおりにいかない場面で手が出てしまうなど、衝動のコントロールができなかったとき、つい頭ごなしに「ダメでしょ!」と言って終わりにしてしまうことがあります。
そんなときには、子どもが落ち着いたところを見計らって、「さっきは何が嫌だったの?」などと一緒に気持ちを振り返ってあげながら、「そうか、悔しかったんだね」「やめてほしいと思っていたんだね」など、子どもの気持ちを言語化する習慣を持つことが有効です。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

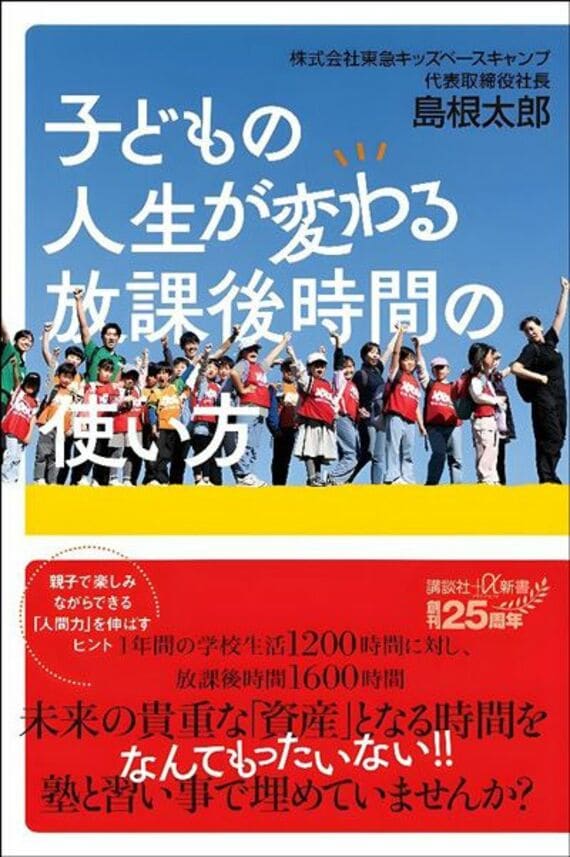






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら