
費用をかけてもその場が長く価値を維持し続けるのであれば回収はできる。小川さんたちはそのために日々地道な努力を続けており、その長期的な視点からすれば新築以上に費用を投じた廃屋再生は決して狂った行動ではない。

それに古いものを壊さず、使い続けていることで地域、社会で得た信用という見えない価値もある。
「建物には土地の人たちの記憶がやどっています。住んだ人、通りかかった人も含めれば何千人もの記憶があり、それを残したことで周囲の人たちからは感謝されました。また、ここをやったことで会社の価値、評価も上がりました。そこにも大きな意味があると思います」
時として地元から反対が出ることもある福祉関連の施設を地元との温かい信頼関係の中でスタートできたのはそのため。ビジネスをしている人であればその環境がどれだけプラスかはお分かりいただけよう。
「建てたらおしまい」ではなく
そして、もうひとつ思うのはそもそも小川さんの先代が、小川さんのように建物や居住者に関心を持ち、手を入れ続けていたら小川文化は廃屋にならなかっただろう、ということ。
昭和の時代には建物は建てたらおしまい、維持管理には長年手を入れないというやり方が主流で、誰もがそれを当たり前と思っていた。そして、それが空き家を生んだ。
令和の今、ハードとともにソフトにも手を入れ続けることを前提にした再生をしなければ同じことを繰り返すことになるが、今、空き家再生に取り組んでいる人がどのくらい、その意識を持っているか。
その意識と積み重ねがあれば、フツーの老朽文化住宅でも人を集め、細く長く稼いでくれる場になりうるのである。

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
















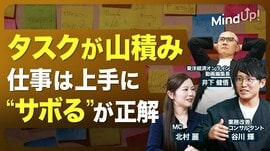















無料会員登録はこちら
ログインはこちら