発達障害の子どもには「できることはやらせる、選ばせる」ことが重要。"決める力"がつけば、保護者の負担も減っていく
これをふまえると、一般的に子どもがどういうときに安心できるかについては、主に以下が挙げられます。
・ 眠る、食べる、トイレといった体の欲求が満たされる
・ やりとりが乱暴でない/叱られずに話が通る
・ 話したいときは、(保護者ができる範囲で)注意を向けてもらって話を聞いてもらえる
・ ルールは一緒に作る。支配されるのではない
・ 困ったことは、怖がらずに相談できる
・ 干渉されずに、好きなことに浸るひと時を過ごせる
「安心して休める家庭」が社会へ出る基盤に
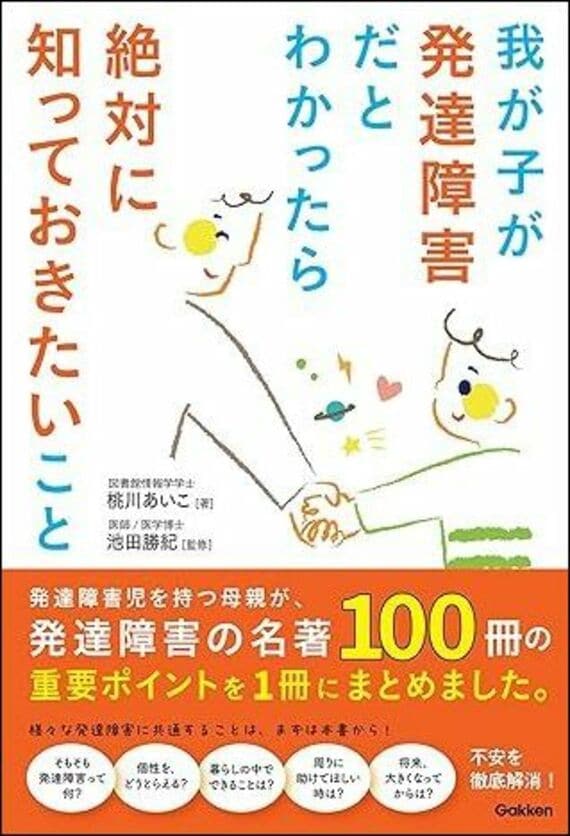
先のことに加えて、特性を持つ子どもがどういうときに安心できるかというと、子どもの「困り感」を理解した次のような要素がプラスされたときです。
・ 頑張ってもできないことや苦手なことがある、と理解してもらえている
・ 自分にとってわかりやすい伝え方をしてくれる
・ わかりにくい伝え方や指示を、しつこく繰り返されない
・ 子どもにとって落ち着ける環境が用意されている
・ やることが前もって伝えられ、あわてたり混乱したりしなくて済む
人生における最初の休憩所は家庭です。子どもはちょっと出かけて、無事に帰ってきて元気をチャージすることを繰り返し、少しずつ行動範囲を広げていきます。
ゆくゆくは社会の中に他の休憩所が増えていくことを願いたいものですが、最初の休憩所である家庭が安心して休める場所であることが、社会へ出ていく基盤になります。家庭が、体と心を休めたいときに休める場所であるよう、気にかけてあげてください。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら