言葉が出ない・話が理解できない…患者数50万人の《失語症》脳卒中の後遺症で名前すら言えなかった男性(65)が"歌の力"で言葉を取り戻すまで
それ以降、関さんはブローカ失語タイプの患者約300人にMIT-Jを実施したところ、約6〜7割の人にある程度の改善が見られたという。
「最初は気乗りしなくても、リハビリテーション が楽しいだけでなく、進歩が感じられ、結果的に効果にもつながるようです。発症後すぐでなく、数年経ってからMIT‐Jに取り組んでも改善の可能性はあるかもしれません。今後、さらに多人数で検討していきます」(関さん)
今後は別のタイプの失語症でも効果の可能性を検討していくという。
失語症の人の「孤独」にもっと理解を
しかし、MIT‐Jは言語聴覚士の教科書で紹介されているにもかかわらず、病院のリハビリテーション現場では、ほとんど普及していない。その理由について、「教科書や論文、講演では伝わりにくかった」と関さんは言う。
2009年に関さん自身が脳梗塞を患い失語症になり、活動が中断したことも普及を阻んだ。
そこで、2022年に日本MIT協会が設立され、関さんが会長になり、実地研修を中心としたセラピストの育成を進めている。現在は全国に110名のセラピストが認定されている(*3)。
だが、医療現場では課題も多い。
現在の健康保険によるリハビリテーションは、入院中と退院後の外来を含め、180日までしか受けることができない。しかし、失語症のリハビリテーションには「3年間は必要」と専門家は口をそろえる。関さんも「5年、10年単位で改善するケースも少なくない」と言う。
さらに、言語聴覚士は新しい職種であるため、必要な人数が足りない。
失語症の人は生活上のコミュニケーションが困難なため、孤独を感じていることが多い。医療現場での課題解決も急務となっている。
*1 特定非営利活動法人日本失語症協議会
*2 本文登場の関さんによると「失語症は全般的に、ひらがなより漢字のほうが理解しやすい」と言う。
*3 日本MIT協会MITトレーナー認定資格者一覧(2025年3月末・希望者のみ)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



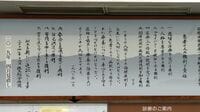



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら