ゴリラのロゴでおなじみ「ゴーゴーカレー」意外にもインドネシアで店舗急増はなんで?世界最大のイスラム教国で「カツカレー」は通用する?
国・地域による食文化の違いが課題
西畑氏が注目したのは、いったん食べたら忘れられない、ゴーゴーカレーの「個性」だった。
「ニューヨーク1号店のオープン当初は、在米日本人のお客さんが多かった。しかしインパクトあるロゴと個性的な味が結びついて徐々に顧客が広がった。来日外国人にインタビューするテレビ番組で『ゴーゴーカレーを食べるために日本にきた』というコメントを見たこともある」
ゴーゴーカレーの個性は、なんとインドネシアでのビジネスにも結びついた。インドネシアの店舗を運営するオーナーも、実はゴーゴーカレーの大ファンだった。ニューヨークで食べたゴーゴーカレーが忘れられず、「自国でも食べたい」とインドネシアでの展開を持ちかけてきたのだという。現地で商業施設などを複数展開しているやり手の実業家だったので、前述したようなスピード展開が実現できた。
他にも海外からの引き合いは数多く寄せられているという。店舗という形だけでなく、学校や工場の給食としての展開もすでに始まっている。スーパーなどでの個食用レトルトパウチの販売も大いに期待できるそうだ。
常に慎重に検討しているのは国・地域による食文化の違いだ。例えば展開が進んでいるインドネシアはムスリムが85%を占めるため、ハラル認証が必要だ。現在のところ地域を選んで出店しており、年内にハラル認証を取得の予定だ。

一方国内においては、客層を女性や若年層にも広げるのが課題。対策としては、他の企業・ブランドやキャラクターなどとのコラボレーションや、SNSによる戦略を講じている。
例えば新規客層開拓のために現在力を入れているのが、ロゴのゴリラを使ったSNS発信。なんとメスなのだそうで、「ゴリ子ちゃん」の名前で活動を開始しているらしい。
大きな可能性が広がる海外市場に乗り出したゴーゴーカレー。そこで最も大きな強みとなるのは、創業者の宮森氏から始まる、強烈な個性だった。そしてバトンを受け継いだ西畑氏が、その個性をITの手法で広く展開していく。日本から世界のメジャーを目指す、同社の今後の動向が注目される。

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら














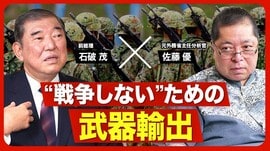
















無料会員登録はこちら
ログインはこちら