ゴリラのロゴでおなじみ「ゴーゴーカレー」意外にもインドネシアで店舗急増はなんで?世界最大のイスラム教国で「カツカレー」は通用する?
世界に通用する3つの理由
西畑氏に成功を確信させたのはどんな要素だったのか。
1つが、日本食ブームの追い風だ。海外の日本食レストラン数は増加し続けており、2023年は約18.7万店。コロナ禍を挟んだ2021年の約15.9万店からも、約2割増加している(海外における日本食レストラン数の調査結果(令和5年・農林水産省)より)。
なお補足すると、上記の理由に加え、少子化による国内市場縮小、円安などを理由に多くの飲食チェーンが海外展開に舵を切っている。ゴーゴーカレーにとっても、これらの要因は切実だろう。
2つ目は、多くの人を魅了するカレーの底力だ。
世界の食を紹介するサイトTasteAtlasの「世界の伝統料理ベスト100」2022年版で、日本のカレーが1位に選ばれ話題となった。寿司やラーメンはよく知られて海外に店舗も増えているが、日本のカレーはまだ広がっておらず、ビジネスの可能性が大きい。
3つ目は、カレーというメニューの再現性の高さ。寿司やラーメンは経験を積んだ職人が必要だが、カレーは完成したルウさえあれば、少ないオペレーションで美味しいカレーライスが提供できる。
そこでものを言うのが「レトルト」という手法。レトルトパウチはかさばらず、常温で1年以上保存できる利点がある。輸送効率もよく、海外にも船便で送ることができる。
レトルトの活用で、人件費を抑えつつ高品質で規模の拡大を見込むことができるのだ。これは西畑氏が経験してきた、ITの図式と同じだ。「技術によって効率化でき、スケール拡大が容易になるのは、ITの世界と似たところがあると感じた」。








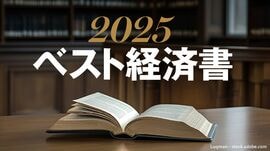





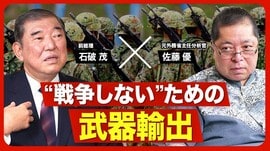
















無料会員登録はこちら
ログインはこちら