「混入はたった1店舗の話」では済まされない…すき家「ネズミ死骸入りみそ汁」他店への影響が免れないワケ
フランチャイズをめぐる衛生面での不祥事で思い出すのが、「大阪王将」仙台中田店での事案だ。2022年7月、同店の元従業員が「ナメクジ大量にいる」などとSNSへ投稿し、大きな注目を集めた。大阪王将は翌月、同店を運営していた企業について、フランチャイズ契約を解除している。
なおその後、元従業員はウソの投稿により店を一時休業させたとして、偽計業務妨害に問われ、2024年10月に仙台地裁が懲役1年の実刑判決を出している。
かつて、従業員による不適切投稿、いわゆる「バイトテロ」が相次いだ。その時も「責任の所在」が問われたが、フランチャイズ契約の場合には、採用は加盟店側の問題だとしやすい。あくまで「加盟店の従業員」であり、本部は一切関知しないといった論理だ。
一方で、オペレーションや教育のマニュアル面を考えると、一概に採用した加盟店の責任ばかりとは言えず、本部サイドのコントロールがどれだけ利いていたのかも重要となる。その責任が本部にあるのか、それとも加盟店なのか。所在が見えづらい状況では、政治家による「秘書がやったから」のロジックのように、しっぽ切りされる可能性もある。
しかしながら、これはあくまで内輪の話でしかなく、消費者は「責任は本部にあるのか、フランチャイズにあるのか」などには、あまり興味がない。
利用者は「すき家」や「大阪王将」といったブランド店で食事していると認識している。顧客は「責任を持つ法人はどこか」ではなく、「どのブランドで不祥事が起きたか」を重視するのだ。
受け入れにくい説明
すき家は今回、「本件は当該店舗の建物構造と周辺環境が重なった事例と当社では捉えています」と説明している。あくまで鳥取南吉方店に限った事象だとの認識を示しているわけだが、この説明はあまり直営方式では受け入れにくい。オペレーションの画一化が前提となるため、店舗個別の事情を乗り越えるような運営が求められるからだ。
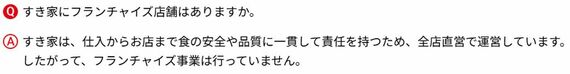
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら