「まるでコストコ」「喫茶店や芝生の広場まである」…。奈良に爆誕「巨大な無印良品」がさすがに凄すぎた
ただ、このように書くと「小売業で『スペース』を押し出しても、結局儲からないんじゃないの?」という意見も出てきそうだ。一見、これは筋の通った指摘にも思える。
しかし、地域と密接に関わり、その地域のコミュニティセンターとして地元住民が頻繁に訪れる場所になれば、それだけで店舗への来店機会を増やすことにつながるのも事実だ。
特に、橿原店にあるような「子ども広場」などを作って子どもの来店機会を増やせば、将来的にその子どもが無印良品への愛着を持つ「ファン」になるかもしれない。既存の小売モデルよりは長期的な視野が必要になるけれど、それは確かに企業の利益に貢献するのである。


実は、良品計画の業績は改善傾向にある。
2024年8月期の決算では、国内事業単体で前年比161%の営業利益を生み出しているし、既存店+ECの売り上げは前年比106%、全店+ECの売り上げは前年比116%で既存店、新店ともに好調である。
もちろん商品ラインの改善や、経営効率の向上など複数の要因があり、こうした地方部への展開だけがその理由ではないだろう。ただ、地方までをも視野に入れた出店が良品計画の業績向上の一つのカギとなっているのは間違いないはずだ。
人口減少社会に対応した「スペースを売る」小売店の変化
橿原店はこうした意味で、現在の無印良品の変化をよく表している。
ブランドの原点に立ち返った商品を数多く取り揃えると共に、コミュニティセンターとしての機能も店舗に持たせる。その両方が、如実に表れている。

いわば、「都心でモノを売るだけの業態」だけでなく、それプラスαで地方・郊外まで含めて「スペースの価値」を売る企業への変貌だ。
そういえば、昨年の4月にリニューアルオープンしたSHIBUYA TSUTAYAもこうした意味で「モノを売る場所」から「スペース自体の価値を訴求する場所」になった。従来、CDやDVDが敷き詰められていた店舗は変わり、展示スペースやポップアップストア、シェアラウンジやカフェを主とした「スペース業」になっている。

こうした変化は、人口減少社会が本格的に到来し、「モノがたくさんある」ことよりも「数少ない人々が集える場所」のほうに価値が出てきた現代の動向を反映しているともいえるだろう。
関西圏にお住まいの方以外は、なかなかふらっと訪れる場所ではないかもしれないが、近くまで立ち寄った際はぜひ覗いてみると面白いと思う。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

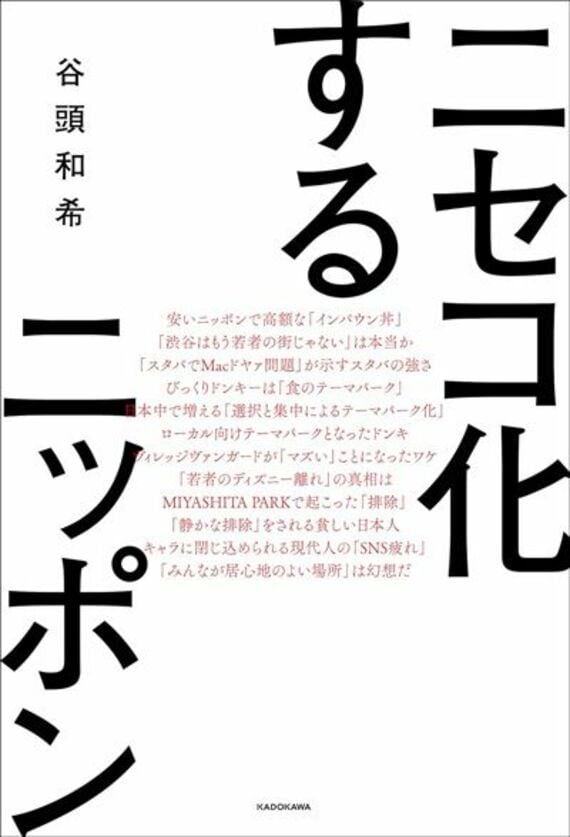






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら