東大生語る「アイス売れると水難事故増加」本当か 「因果関係」を正しく理解することが大切だ
最初の例に戻ってみましょう。「朝ごはんをしっかり食べている子どもは、成績がいい」と言われたとき、みなさんは安易に「朝ごはんをしっかり食べている“から”、成績がいい」と脳内で読み替えてはいませんか?
確かに、朝ごはんをしっかり食べたほうが、十分な栄養を摂れる脳の発達にいいのかもしれません。しかし、本当にそれだけでしょうか?
実は、この「朝ごはんをしっかり食べている」ことと「成績がいい」ことの間には、必ずしも因果関係があるわけではないと考えられます。
朝ごはんがしっかり食べられるということは、「朝起きるのが早い」ということで、本当は早寝・早起きの生活サイクルが成績向上につながっているのかもしれません。
あるいは、何らかの食品(たとえば卵や納豆など)を食べることが成績向上につながっていて、たまたまそれを朝に食べる人が多いのだという可能性もあります。
また、きちんと朝ごはんを子どもに用意できている家庭は、そうでない家庭と比べたとき、食事以外の面でも子どもに優れた環境を提供している可能性が高いという見方もあります。そうすると、教育環境という点で、朝ごはんをしっかり食べている子どものほうが有利な状況にあるのかもしれませんね。
因果関係が成立しているかは判断が難しい
このように、因果関係を推定するというのは本来、とても難しいことなのです。これが科学的な実験であれば、あるひとつの条件だけを除いて、それ以外はすべて同じ条件で対照実験を行うなどすれば「本当にその要素が原因として結果に作用しているのか」を判断することができるかもしれません。
しかし、社会現象などの対照実験を行うのが難しい事象に関しては、その要素と結果の間に因果関係が成立しているかどうかを調べるのは非常に困難です。
アイスと水難事故の例のように同じ原因から生じた結果同士であったり、見かけ上の相関関係はあるけどまったく無関係だったり、「AだからB」なのかと思ったら、実際は「BだからA」だったりもします。
「アイスの売り上げが多い日は水難事故が多いから、水難事故を減らすためにアイスの販売を禁止しろ」と言われても困ってしまいますよね。
でも、それに似たような思い込みを、私たちは無自覚のうちにしてしまいかねないのです。
誤った思い込みから抜け出すためには、一度立ち止まって「本当にそうなのか?」と自らの思考を問い直すことが必要です。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

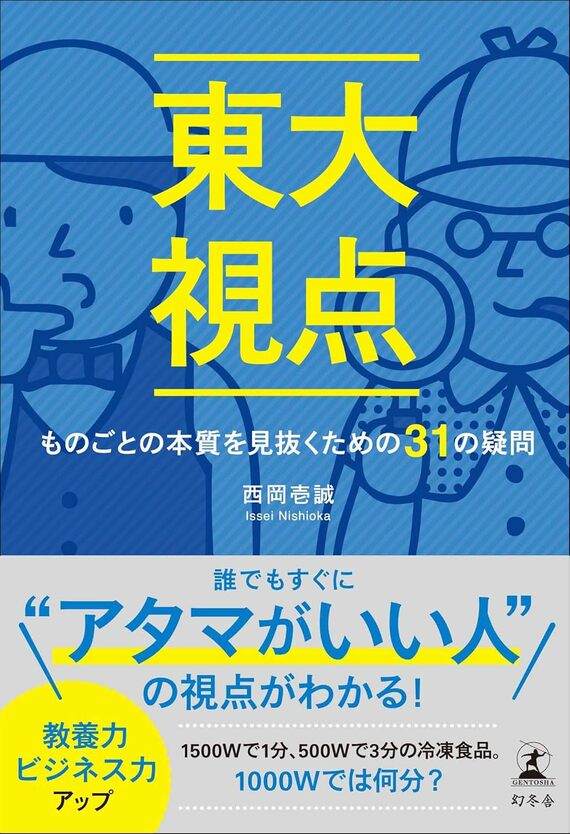






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら