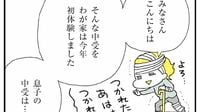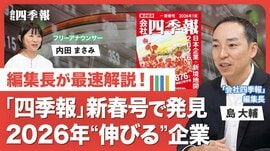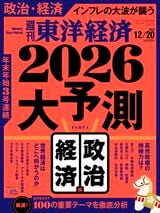共通テスト監督者「トイレ立ち入り」は苦肉の策? 「中学受験」でも頻出"カンニング"の実態と対策
監視の目を厳しくしなければと考える人もいると思いますが、なるべく誰も傷つけずに不正を減らすために、まずは受験生を疑わずに済む環境をつくるという発想が大事です。
金属探知機を使ってスマホを会場に持ち込めないようにしたり、たとえ持ち込んでも、(携帯電話の電波を妨害する)電波ジャマーによって通信できないようにしたりといった対策は有効でしょう」
カンニング問題を根本的に解決するには
不正防止の本質としては、環境の整備だけでなく、子どもたちの「マインド」に働きかけることも重要だ。
矢萩氏によると、中学生以上では、カンニングを“武勇伝”として仲間うちで自慢したがる生徒や、むしろ自らの知恵が詰まった“ハック”として遂行する生徒が出てくる。
一方、小学生の場合は、「悪い点数をとって親に怒られるのが嫌だ」といった、勉強に対する主体性のなさが背景にあることが多いという。
「『勉強は自分の成長や幸せのためにするものであって、成績や偏差値は指標でしかない』『カンニングで目先の点数を上げて得をしているように見えるのは大間違い』ということを子どもに理解させないと、根本的解決になりません。
そのためには、周りの大人たちが『努力すれば必ずその分だけ成長する』『お前は大丈夫だ』と、本気で信じてあげること。自己肯定感がきちんと育っている子は、カンニングなんてしないものです」
カンニングに関する報道が出ると、摘発方法についての議論が活発になりがちだが、教育のあり方や子どもとの向き合い方について考える良い機会にもなるはずだ。
(AERA dot.編集部・大谷百合絵)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら