冤罪の原点「免田事件」が私たちに問うもの 本人が死去しても晴れない「冤」を雪ぐために
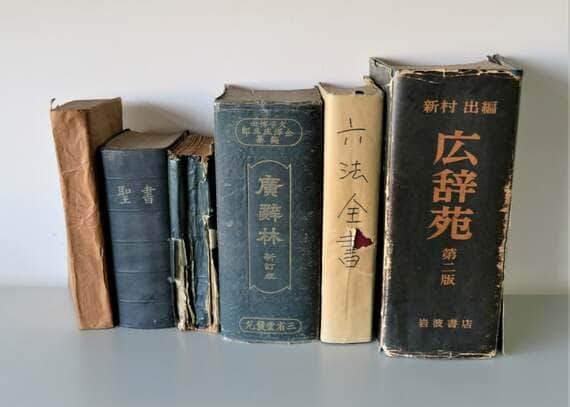
「被告人は無罪」――たった6文字の言葉だが、冤罪を訴え続けている一人の人間にとっては何ものにも代え難い、万斛(ばんこく)の思いがこもる言葉であろう。
2024年9月26日、静岡地裁(國井恒志裁判長)は「袴田事件」の再審判決公判で確定死刑囚の袴田巌さん(88)に無罪を言い渡した。事件発生から58年、死刑確定してからでも44年が経過していた。何という時間の長さだろうか。
事件の発生は1966年6月。静岡県清水市のみそ製造会社の専務宅から出火、焼け跡から専務ら4人の遺体が見つかった。強盗殺人、放火事件として捜査した静岡県警は同年8月、元プロボクサーで同社従業員の袴田さんを逮捕。袴田さんは公判で無罪を主張したが、静岡地裁は1968年に死刑判決、1980年に最高裁で確定した。
その後、事件は複雑な経過をたどる。2度目の裁判のやり直し・再審請求で静岡地裁が再審開始を決定、袴田さんを釈放したものの、東京高裁が取り消す。これに対して最高裁が差し戻したため東京高裁で審理がやり直され、再審開始となったのだった。
2024年9月の再審無罪判決で國井裁判長は捜査陣による「証拠の捏造」を挙げたが、検察はこれに強く反発、控訴を断念した際の検事総長談話でも「重大な事実誤認」と最後まで納得しなかった。
検察はその後、事件を検証する「報告書」を公表したが、事件の根底を剔抉(てっけつ)するに十分なものではなかった。無辜(むこ)の人を罰しない司法をどう作り上げるか、死刑制度はこのままでいいのかなど、冤罪事件が浮き彫りにする課題への取り組みは待ったなしである。
原点としての免田事件
「被告人は無罪」という言葉を、確定死刑囚として日本で初めて聞いたのは免田栄さんである。1983年7月15日のことだ。私はその時、判決言い渡しがあった熊本地裁八代支部で地元熊本日日新聞社の社会部記者として取材していた。
死刑が確定した後に再審無罪となったのは袴田さんで戦後5人目だが、その嚆矢(こうし)が免田さんなのである。免田さんの後、財田川事件(香川県)、松山事件(宮城県)、島田事件(静岡県)、そして今回の袴田事件と続く。
免田事件はどんな事件だったのか。
1948年12月30日未明、熊本県人吉市の祈祷師(きとうし)白福角蔵さん方で一家4人が殺傷されているのが見つかった。夫婦2人が死亡、幼い姉妹が重傷を負った。捜査は難航したが、聞き込みなどから不審者として免田さんが浮上、翌1949年の1月16日、強盗殺人容疑で逮捕される。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら