「移民」「外国人」と聞けば嫌悪感を抱く日本人の本性 「アジア人」と自覚すればつまらない感情は消え去る
この本は、明治以来日本がもってきたコンプレックスそのまま表現したものにすぎない。近代化のために日本固有のものを投げ捨て、ひたすら西欧模倣に励んできた日本人を、ある意味西欧人的な目から見た書物だといえる。
ルース・ベネディクトの『菊と刀』(1946年)以来の、紋切り型の日本人観を表現しているだけの本であるがゆえに、欧米でも歓迎されたともいえる。
日本の大使館の多くには日本文化センターが設置されている。そこではなぜか英文図書が並べられている場合が多いが、不思議なことに多くは西欧人が書いた日本紹介の書物である。そこにはあまりいいことは書かれていない。
しかし、外国人が書いているのだからまあ許される。ただ、日本人が、それも大使という外交官が書いたのだからスキャンダルとなったのは当然であった。
ただ、この本の内容は、身も心も西欧に捧げている日本のエリートのコンプックスの表現にすぎないということだ。経済成長まっしぐらの一般庶民にとってこんな日本人観は無意味なものであったことは間違いない。歓迎はしなかったが、問題にもしなかったのだ。
『素顔の日本』が刊行されてからわずか10年で、日本は西欧政界を凌駕する経済大国になり、エズラ・ヴォーゲルの『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979)という書物まで出版されたのだ。当時の日本人の寛容さとたくましさに脱帽すべきだろう。
日本での翻訳が少ない西欧の自己反省本
もちろん、それ以降の日本人は、かつての自信はいつのまにか薄れ自暴自棄に陥り始めた。だから、移民や外国人を忌み嫌うようになったのだろう。とりわけ、その批判は、飛ぶ鳥を落とす勢いの近隣のアジア諸国に対して、向けられはじめたのだ。
西欧社会においても、アジア経済の発展は脅威をもって見られている。それはある種、偏見に満ちた言説でもある。19世紀を覆ったアジアへの偏見の再版も多くある。これらは翻訳書の中に見られる。
しかし、西欧の自己反省を伴う書物もある。もっとも日本においてそうした文献が翻訳されることは意外と少ない。
アジアの文献を翻訳することがあまりに少ない日本であるから、日本人のアジアに対する見方が19世紀の西欧的偏見に占領されてしまい、大きな誤解を生み出しかねない。
アジア経済の発展が、アジアの技術進歩のたまものであるとすれば、アジアの書物がどんどん翻訳されなければならない。しかし、アジアの書物の翻訳はあまりにも少ない。

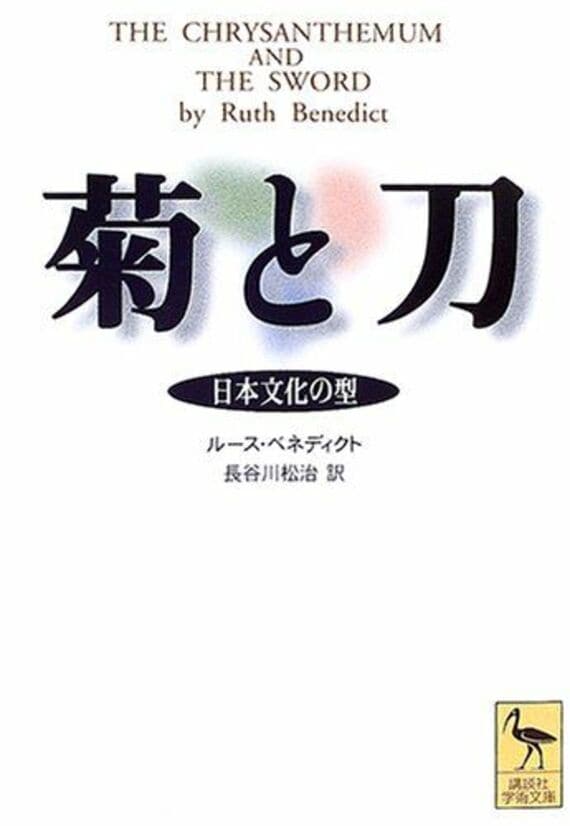
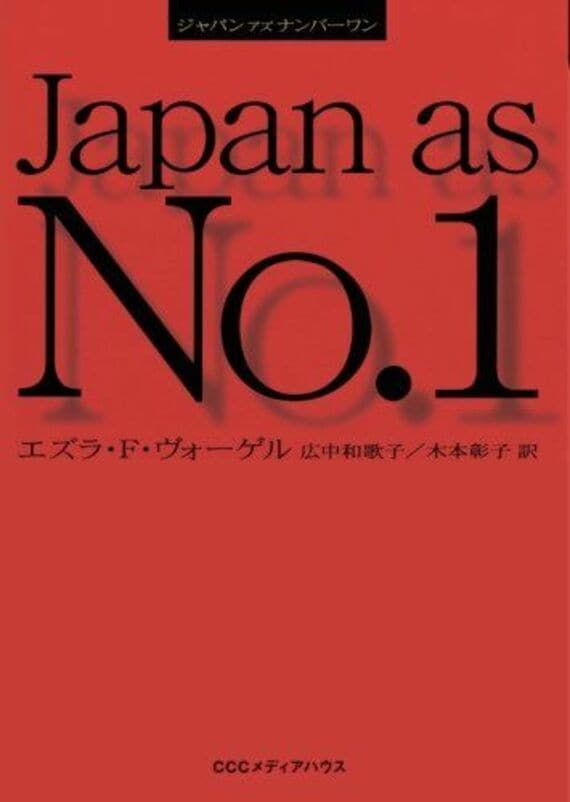
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら