国民生活センターには、未成年を中心に「子どもが勝手に投げ銭をしてしまったので請求を取り消してほしい」という相談が数多く寄せられている。
「小学生がネット上の解説動画を見て子ども用スマホのフィルタリング機能を解除してしまい、4万円を課金していた。本人にも課金したという認識がなく、取り消してほしい」といった内容が目立つ。
一方で中には「ライブ配信アプリで『7000円を投げてくれたら手書きの手紙を出す』と言われ、言われた額を投げ銭したが『もっと投げてくれないと特典を送らない』と言われた。返金してほしい」(20代男性)など、大人から相談が寄せられることもあるという。
推し活は「活力」になるが…
しかし、投げ銭の規制は進んでいないのが実態だ。ネットやギャンブルへの依存に詳しい精神科医の西村光太郎氏によれば「複数の配信プラットフォームが配信者側・視聴者側ともに年齢制限を設けておらず、依存症の引き金となりやすい。また、成人と未成年者との不適切な接触機会の温床になっている」という。
「推し活依存のように人間関係への依存症が背景にある場合、なかなか復帰が難しい。とくに成人の場合は幼少期の生育環境が影響している可能性が高く、回復に時間がかかる」(西村医師)のが実態だ。
依存症の専門治療を行う久里浜医療センターでは依存症患者に対し、認知行動療法と運動プログラムを行うなどで日常生活への復帰を促している。中高生の患者向けには一定期間スマホを持たない「治療キャンプ」を実施し、インターネットから距離を置く術を身につけるよう、アドバイスをしている。
推し活は多くの人にとって生活していくための活力を得る機会になっている。一方で資本の論理によって際限なく投下されるグッズやコンテンツ、あるいは投げ銭へのプレッシャーとどのように向き合うか。
コンテンツの作り手やプラットフォームなど企業側はもちろん、消費者にとっても推し活との適切な距離を考えるタイミングが来ている。
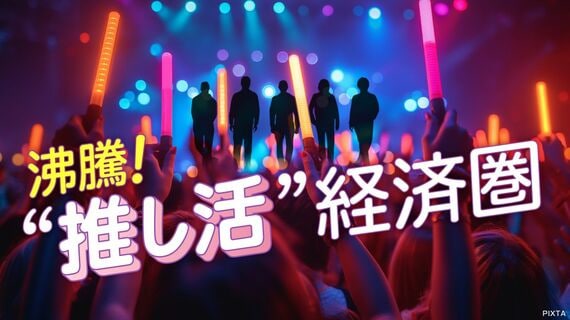
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら