渋谷がもはや「若者の街」じゃなくなった深い理由 むしろ「若者が集う場所」はつねに変遷してきた

ふとした用事で渋谷を歩いていたときのことだ。スクランブル交差点を見回して気づいたことがある。
「若者の姿が少ない」
20代と思しきカップルなどはちらほら目につくが、10代と思しき人々は少ない。高校の制服を着ている人となると、ほぼいないような気がする。そして、外国人がとても多い。
都市開発と変化し続けている「若者の街」
私だけが気付いたことのようではないようだ。
ネット上を見てみると、「渋谷から若者が消えた」「渋谷はもう若者の街ではない」といった記事が散見される。中には「渋谷はおじさんの街化している」という、少し過激な表現で、こうした渋谷に集う人々の変化を解説している記事もある(「渋谷は「おじさんの街」化、新大久保は10代が溢れる若者の街に…予期せぬ社会的背景」/「ビジネスジャーナル」2023年7月3日)。
この記事の中で、オラガ総研代表の牧野知弘は、近年の渋谷の再開発によってオフィスが増加したことや、ハイブランドショップが増えたことをその原因として挙げている。渋谷の都市開発のターゲット層が10代などの若者ではなくなってきている、という。
いずれにしても、このような言説は真新しいものではなく、ここ数年でしばしば語られることだ。しかし、そもそも私たちが忘れていることがある。それは、「若者の街」はつねに変化し続けている、ということだ。
「街」は変化し続けるものであり、そうであれば当然「若者の街」も変化していくはずだ。そこでこの記事では、渋谷を軸として若者の街がどんな理由で、どのように変化してきたのかについて考えてみよう。














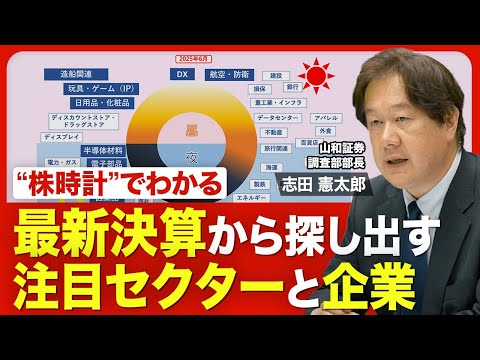
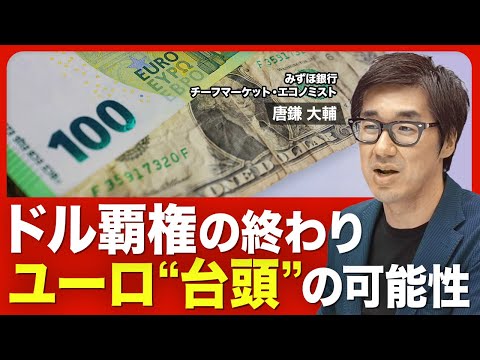



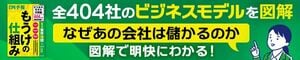
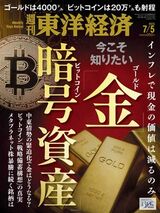









無料会員登録はこちら
ログインはこちら