焦りでうまく計算できないこともあります。たいていの人は、焦らされて緊張感が高まると課題がうまくできないものですが、発達障害のある子どもたちはなおさらです。「早く答えなくちゃ!」と思うと、さらにミスがふえます。まずはカードを順番に並べて、「答えられた!」をふやしていきます。
次に順番をシャッフルして、緩やかに難度を上げていくといいでしょう。計算カードは種類によってまちまちですが、だいたい30枚くらいあります。カードが少なくてもやらないよりはマシなので、カードを10枚だけ抜き取って机に置き、それに答えるというのもいい方法です。
指先が不器用でカードをめくるのが嫌になってしまったり、脳に負担がかかってうまくめくれなかったりすることがあります。そんなときは大人がかわりにカードをめくり、計算に集中できるサポートをしましょう。

最初は計算カードの枚数を絞り、「1+1、1+2、1+3」と順番に並べたところから始めます。覚えるくらいになったら、次はランダムに並べたりして、少しずつ難しくしていきましょう。
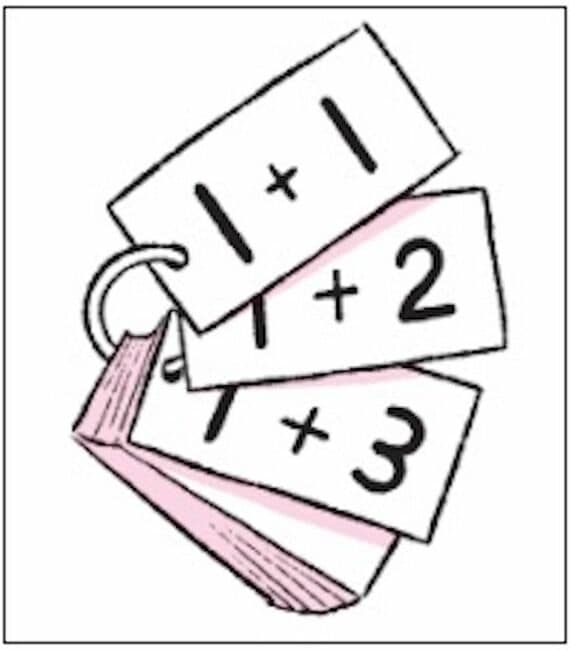
国語 音読「読みやすくなる道具を使う」
定規や自分の指も、文章を読みやすくするための道具になります。専用のルーラーを使ってもいいでしょう。
● 定規を文の横に置いて、今どこを読んでいるかわかりやすくする
● 読んでいるところを指で押さえたり、なぞったりする
● 詰まったときに、あいうえお表の該当文字を指し示す
● デジタル教科書(デイジー)※を使う

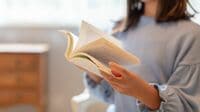





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら