システムをつくった後も、どういった運用をするか決める必要がある。

](https://m.media-amazon.com/images/I/51eaDzwou3L._SL500_.jpg)
「運用」。さまざまな意味に取られがちだが、ここでは開発したシステムを動かし続けることと捉えてもらえばよい。
実は日本のITは運用に多くのコストをかけている。日本情報システム・ユーザー協会の「企業IT動向調査報告書 2022」によると、企業のIT予算に対する、維持・運営と新しい施策展開との割合は76対24。つまり運用費が圧倒的に多い。では「運用」で何をしているのか。例え話でわかりやすく説明してみたい。
荷物を配送するトラックをシステム、その積み荷をデータとしてみよう。トラックの車体がハードウェア(サーバーなど)、ドライバーや車の機能がソフトウェアだ。
実施していることは多岐にわたる
まず、このトラックは高速道路をずっと走り続けないといけない(システムはずっと稼働し続ける)。当然車体は傷むため、故障による交換や、予防保守が必要となる。完全に故障したときに備えて予備トラックの準備も必要だ。
大量の荷物を積み込むと、出し入れにも時間がかかる。間違った荷物が入ってきたらフォローしないといけない。不審者が侵入していないか、荷物が盗まれていないかも気にしておかないといけない。ほかのトラックとの連携も必要だ。

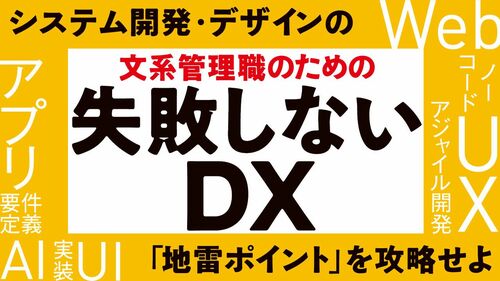

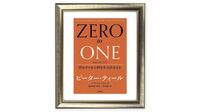





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら