どんな相手と開発を進めるかによってシステムの成否が決まる。

](https://m.media-amazon.com/images/I/51eaDzwou3L._SL500_.jpg)
誰とDXやシステム開発を進めるか。この選択にも地雷ポイントがある。開発能力が弱い先に大規模案件を依頼してしまったり、自分でもつくれるシステムを大手開発ベンダーに依頼して費用対効果が合わなくなったりと、実際あらゆる失敗が起きている。
システム開発の依頼先は下表のとおりだ。まず社外に発注するか、社内で開発するかに大別できる。
社内なら情報システム部などシステムエンジニアを擁する部署に依頼するのが王道。何よりも自社業務に精通しているのが大きい。ただ多くの案件を抱え、追加で開発を頼む余裕がないことも多い。
もちろん自分でつくる、あるいはシステムが得意な同僚に頼む手もある。Python(パイソン)など比較的簡単なプログラム言語や、プログラミングが不要なノーコードを使えば、ちょっとしたツールはつくれる。依頼の手間が省けるし、コスト面でも安く済む。
しかし属人化することが多く、セキュリティーなどへの理解不足によるリスクも大きい。

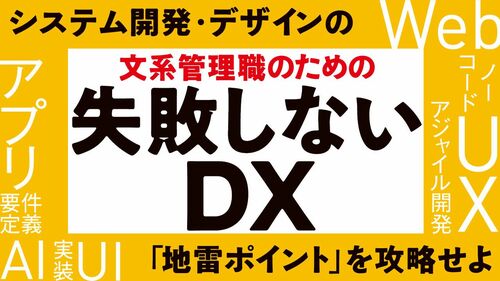

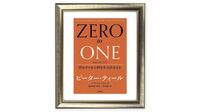





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら