
プログラミングの基本構造を学ぼう
ビジネスパーソンがプログラミングを身に付けるメリットは大きい。定型業務を自動化できるだけでなく、課題を解決するために構造を要素分解し、どの作業をどの順でどう組み合わせれば解決に近づくかを論理的に考える「プログラミング的思考」も養われる。
プログラムは、コンピューターに実行させたい処理を命令文として書く。命令文の種類は事前に決まっており、適宜組み合わせて目的の処理を実現するのが肝だ。基本構造は「順次処理」「反復」「条件分岐」の3つしかない。
1つ目の順次処理は、命令文が上から順に実行されるという意味だ。[図1]を見てほしい。ロボットをスタートからゴールに誘導するプログラムを書くとする。使える命令文は「1ブロック直進」「右に曲がる」「左に曲がる」の3つで、複数利用可能とする。3つの命令文をどう並べればよいか。
正解例がプログラム1~3だ。いずれも上から順に実行されるとゴールに着く。ただし、好ましいのは記述量が少ないプログラム1だ。命令文の数が少なければ、コンピューターの処理が速くなる。

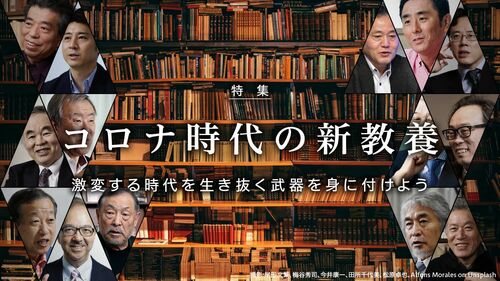
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら