しかし、である。このような意味での戦略は重要であるが、実際に、日銀が行なう出口戦略・広報戦略以外の出口における行動というのは、全く異なっているのだ。どういう意味かというと、それは戦略的にはなり得ないのであり、戦略ではないのである。それは、上に触れたようにオペレーションに過ぎない。そして、オペレーションを通じて行なう以外、出口戦略というのはあり得ないのだ。
国債などの買い入れをやめるしかない
どういうことか。出口戦略とは、現在行なっている、量的・質的金融緩和の効果がありすぎて、景気が過熱してきたために、方向転換をして、緩和から引き締めへ向かうのであるが、量的・質的金融緩和の終了という出口へ向けてどのように進むか、ということと理解されているが、投資家との関係に対する考慮を除けば、実際に出口へ向かうためには、国債などの買い入れをやめること以外に道はないのである。道はないというより、国債などの資産を大量に買い入れることが量的緩和であり、米国FRBは量的緩和という言葉を使わず、バランスシートポリシーと呼んでいる。
質的緩和というのは、日銀独自の言い方であり、これこそ戦略の部分であり、政策をどう見せるか、というところにポイントがあったのだが、その成否、賛否にかかわらず、出口に置いては、それは広報戦略以外には特に存在しない。
したがって、日銀のアクションとは、国債の買い入れをどう変化させるかということにかかっているのであって、出口ということは、緩和を縮小していき、引き締めに向かうのであるから、現在米国FRBが行なっているように、まず買い入れ額を減らしていき、買入を止め、そして、次には、国債を売り出していく、いわゆる売りオペを行なうことになるのである。
その中で、どのタイミングで金利を引きあげるか、どの金利を引き上げるか、ということが問題になってくるが、これも量的緩和局面が終了した後の話なので、量的緩和の出口においては、戦略的になりえず、淡々と国債の買入をやめていくしかないのだ。ここで、J-REITや株式もあるが、量的にはごく僅かなので、ほとんど関係がない。要は、国債の買入をどのようにやめていくか、どのように売りオペを行なっていくか、ということに尽きるのである。
したがって、国債の買い入れの変化だけが量的緩和の出口において日銀が行なえることなのである。しかも、その場合に、売りオペは現実的にはほとんどできないだろう。厳密に言うとこれは正確な言い方ではないが、現在投資家たちが想定しているような、実質的に意味のあるインパクトを持って長期国債を日銀が売ってくることはないと考えるべきである。なぜなら、日銀の出口戦略とは、「期落ち」をひたすら待つことしかないと思われるからだ。
「期落ち」とは、保有している国債の満期が来ることである。満期が来るから、それは自動的に国債から現金に置き換わる。売りオペと同じように国債の保有量が減るが、それは市場で売るのではなく、何もしない、ことにより生じるのである。もちろん、すべての国債に満期はあるから(ないものもあるが、現在の日本国債にはそのようなものはない)、現在も期落ちは常に起きているのであるが、その分をロールオーバー的に買っているので期落ちが問題にならないだけだ。米国FRBも、オールオーバーを今のところしているが、これをいつやめるかが焦点となっているように、これは重要なことだ。

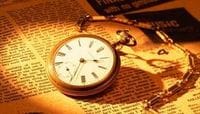





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら