「21世紀の資本論」が問う、中間層への警告 日本に広がる貧困の芽とは何か
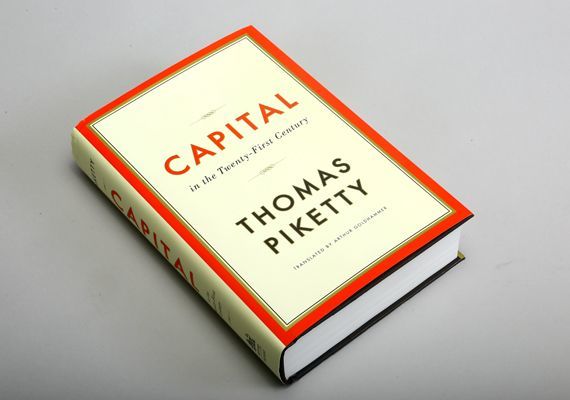
一匹の妖怪が世界を徘徊している。ピケティという名の妖怪が――。マルクスの言葉をもじってそう言いたくなるようなブームが、欧米で巻き起こっている。フランス経済学校のトマ・ピケティ教授による『21世紀の資本論』が、経済書としては異例の大ヒットとなっているのだ。英語版で約700ページにも上る本格的な経済書だが、特に米国では書店から蒸発するように売れ、出版社が増刷を急いでいる。
マルクスの『資本論』をほうふつとさせるのはタイトルだけではない。本書は「資本主義は格差を拡大するメカニズムを内包している。富裕層に対する資産課税で不平等を解消しなければならない。さもなければ中間層は消滅する」と主張。この主張が米国では、「ウォール街を占拠せよ」運動に代表されるような格差の議論に結び付き、一般市民を巻きこんだピケティブームが巻き起こっている。米国の保守派は「ソフトマルキシズムだ」と反発するが、ポール・クルーグマンやロバート・ソローなど、ノーベル賞受賞経済学者はピケティの実証的な研究を高く評価している。
中間層が消滅する未来
同書は日本でも2014年内をメドに、みすず書房から出版される見通し。書店に並べば、国内でも話題の一冊となることは間違いない。なぜなら、中間層が消滅する資本主義の暗鬱とした未来は、私たち日本人の足元でもさまざまな現象として現実味を帯びつつあるからだ。
たとえばリストラ。たとえば高齢化した親の介護、自身の病気。こういった不運だが誰の身の上にも起こるライフイベントは、収入の激減や支出の急増を招き、中間層の人生設計を容易に狂わせる。何も起こらなくとも、年収1000万円クラスのアッパーミドルにとっては、社会保障コストの負担が増える趨勢だ。
アベノミクスで景気が回復したといわれるが、好景気を実感できている日本の中間層はどれぐらいいるだろうか。かつては1億総中流と呼ばれ、誰もが成長を実感し、ささやかながらも豊かさを享受できた社会。それがすでに過去のものというのは、現代に生きる日本人の実感といっても、いいのではないか。好景気を実感するよりも、人生という長いレースで貧困側に転落しないか、その不安におののいている人のほうが多いのではないだろうか。


































無料会員登録はこちら
ログインはこちら