「少しでも多くの地域の人に来てもらい、その地域の発展の参考になれば」と考え、貴重な時間を使って視察見学を受け入れる地域はたくさんあります。にもかかわらず、現地でのトラブルに始まり、視察後は「現地へのフィードバックゼロ」というのは、受け入れた地域も非常に消耗するものです。
実際、本気で視察見学に訪れる人は、ほとんどの場合「少人数」「自費」で申し込んで来ます。このように、本気の人というものは基本動作からして違うのです。
「若手中心」&「成果直結」の仕組み作りを
コロナ禍で、オンライン視察をいったん若手に任せたのですから、これこそチャンスとしたいところです。本来、視察して参考になった点を現場ですぐに生かせる若手にこそ、国内、海外問わずに視察に向かわせることのほうが大切なのです。
もし視察がリアルに戻っても、若手を中心に視察に行かせるとともに、現場でその学びを実践する仕掛けを徹底してほしい。まず、意味不明なお偉いさんがくる視察見学は、人数を半分以下にしましょう。お偉いさんは自分でもお金を持っているのですから、視察するなら自身の財布で別に行ってもらいましょう。
ここは少人数の若手、とくに現場の一線で頑張っているような人たちにこそ、予算をさいて見聞を広げさせるほうが、組織の発展につながります。そのときにも完全にタダにするのではなく、少しでもいいので適切な負担は若手もすべきでしょう。それがなければ、若手でさえ、本気にはなりません。
同時に、人数を半減させたことで生じる「予算の余剰」を現場に生かすために投資すべきです。現地で学んできたことを生かすにしても、手元に一銭もなければ実現が難しいものは多々あります。視察予算の半分をプールし、視察から戻ってきた若手メンバーに新規事業を立ち上げさせたり、既存事業の改善につなげさせるため、しっかり投資しましょう。
コロナ禍によってあぶり出された、視察という名の「タダ飯旅行」というひどいリアルを見直し、若いメンバーに視察と挑戦の機会を作り出す。そうすれば、地域は大きく変わります。地域の未来は、人に対する投資以外にありません。
コロナ禍が明けた後には、本当の意味での「視察」が行われることを期待します。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

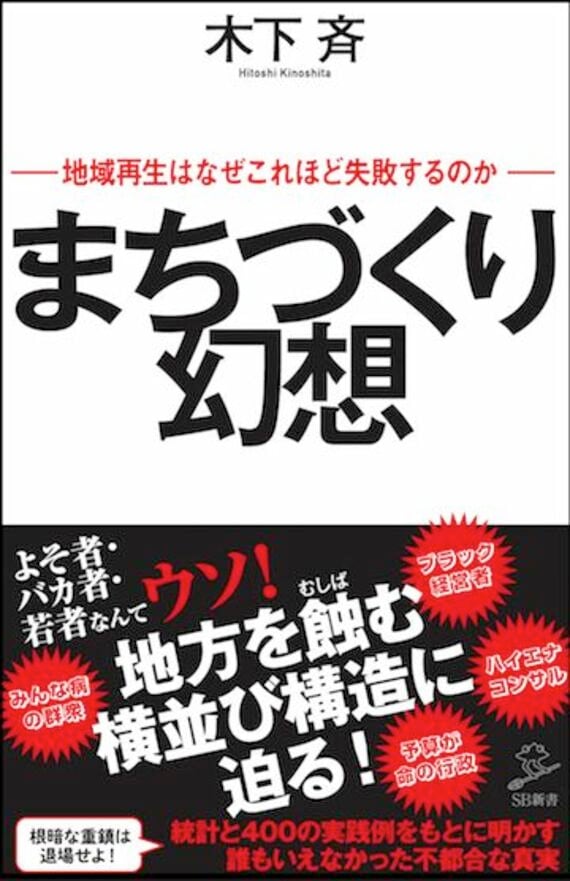






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら