実はアメリカでも、ワクチンに不安や不信感を抱いて「接種を受けない」という人々が、若者、黒人、女性、最終学歴が高卒以下の集団に、相対的に高い割合で存在するという調査結果がある。そうした人々をどうやって受ける気にさせるか?という議論が続いている。
接種を義務化すればいいと思われるかもしれない。しかし、アメリカ国内における1つの壁は、新型コロナワクチンが通常の承認プロセスを経ていないことだ。いずれも当局による「緊急使用許可」(EUA)により使用が認められたにすぎず、義務化には安全性と有効性のデータが足りない。
それどころか、義務化は「逆効果」との指摘もある。ジョージタウン大学のローレンス・O・ゴスティン法務博士は、アメリカ医師会雑誌(JAMA)で以下のように述べている。
「義務化はかえって国民の支持を失いかねません。反発を引き起こし、ワクチン接種を減少させることさえあります。将来においては義務化が有用かもしれませんが、ワクチン接種が広く支持されていない集団で義務化すれば、逆効果になる可能性があります。リスクコミュニケーションの目的は、個人の選択を尊重し、意思決定に情報を提供することです。義務化は、個人の自律性を無視し、リスクコミュニケーションの本質を根本的に覆すものです」
若者たちによる「発信」が重要
だったらどうすればいいのか? ワシントン・ポスト紙は、「ポリオワクチンをプレスリーが打ったように、若者に人気のあるビヨンセに新型コロナワクチンを打たせたらいい?」と提案。およそ60年前、アメリカではポリオワクチンの普及のために、エルビス・プレスリーが担ぎ出されたことを紹介した。
だが同紙は、プレスリーの宣伝だけがポリオワクチンを普及させたわけではないことも指摘している。突破口はむしろ、10代の若者たちの協力を得たことだった。ポリオワクチンを推進する非営利団体はまず、若者たちを招いてヒアリングを実施。注射に対する恐怖や健康への過信など、彼らの仲間が接種に乗り気でない理由について丁寧に把握した。
重要なのはその後、若者たちにワクチン推進活動への参画を依頼したことだ。彼らは理解し、同意し、10代の活動グループを結成して、予防接種を受けた証明を持つ人のみが参加できるイベントなどを開催していった。その際、ワクチンのPRに大いに役立ったのが、「10代によって、10代向けに、10代の言葉で書かれた」印刷媒体だったという。
「プレスリー+若者グループ」作戦の効果は絶大で、1950年代後半には数百万人の10代男女がポリオワクチンを接種し始めた。
現代に置き換えれば、プレスリーはインフルエンサー、印刷媒体はインターネットということになるだろう。そして重要なのが、若者たちによる発信だ。一部の強力なインフルエンサーがYouTubeなどで発信するのと同時に、社会に貢献したいという気持ちのある中高大学生にSNSで働きかけてもらう。
ワクチンを不安がる人々には丁寧な説明が必要だ。ただ、その言葉が届かなければ、届いても伝わらなければ、意味がない。情報を届けたいコミュニティの中に理解者を作り、自分たちの言葉で説明をしてもらう。そうして現代型の“草の根運動”を広げられるかどうか。
ワクチン政策を固め、ワクチンを確保し配置し、なんとか接種・管理体制を整えることができたとしても、最後は接種を受ける人にかかっている。「受けたい」「受けなければ」と思い、足を向けるかどうかだ。その問題意識を共有したい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



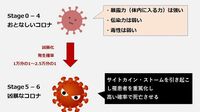




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら