
アフリカを本当によくするのは、世界銀行でも、国連でも、JICAでも、外国のボランティア団体でもない。外部の力というのは、アフリカの広大さと複雑さに比べたらあまりにも微小だし、しょせん、外からものを言うコンサルタント集団が大部分で、行動を起こす主体ではありません。
主役はアフリカの人々です。どれだけ多くの人々が、まさに司馬さんが書かれたように、青空をめがけて坂を上っていこうという楽天主義を持って、坂を上っていくための努力と、チームを強くするための自己犠牲ができるかどうかにかかっていると思います。
こういう集団での努力以外でも、「この技術が世界を救う」みたいなウルトラCも、ごくたまに起こるのかもしれません。でも、その天佑を生かせるのは、アフリカの人たちの強い意志と行動が伴うときだけだと思います。
たとえば、仮に水がまったくなくても作れるコメの品種が発明されたとして、それが水不足のサハラ砂漠の真ん中の国に持ち込まれたとしましょう。しかし、それを生かすには農場を開墾しなければいけないし、そもそもそのコメの苗を買うためのおカネを貯めるのは、ほかでもないその国の人たちです。
そして、農家の人たちは、農場を持続的に経営できるように日々一所懸命働き、政府はその農場がうまくいっても、追加の税金や賄賂を巻き上げないようにしなければなりません。
また、そもそも収穫したコメを保管する倉庫や精米所のキャパシティも上げていかないと、コメをいくら作っても意味がありません。そうやって儲かったおカネを、さらなる産業発展のために再投資したり、教育や医療に投資するなど、持続的な発展につなげていくのは、一人ひとりの努力以外のなにものでもありません。このように、単発的な投資や技術がいくら起こってもだめで、それらが本当に生きるには、社会全体の集団的な力が必要になります。
「アフリカが成長できないのは、銀行が積極的におカネを貸さず、金融へのアクセスがないからだ」という向きも多いでしょう。でも、明治の日本に、今のアフリカよりましな金融アクセスなんてあったでしょうか。
そうなると、司馬さんが書かれた内容は、一見、単純な議論に見えますが、実はかなり本質をついていると思うのです。最終的には、国民一人ひとりが楽天主義をもって、どれだけ総合的な努力ができるか、ということなんじゃないかと思います。そして、その努力は、一部の人だけがやるのではなく、「せーの」で一斉に起こる必要があるでしょう(でないと一部の人だけが損をするだけに終わる)。それが、アフリカでは本当に難しい。
震災の年の夏に日本に帰国し、節電の徹底ぶりに感銘を受けましたが、国民全体で一斉に努力して国全体の使用電力を大幅にカットしてしまう、こういうことができるのが国の底力であり、国の発展に直結する最大の要素だと思うのです。


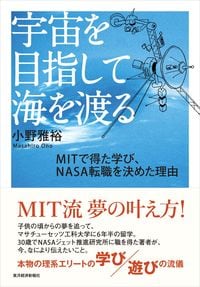




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら