上司は機嫌で「べき論」の境界線を変えてはならない
以上を踏まえ、ここからは、組織内における「べき論」について考えたい。組織において、上位に立つものが「怒るor怒らない」を選択する「べき論」の境界線を日によって変えると、部下たちに混乱や不信を招く。チームの生産性や部下のモチベーション維持にも大きな影響を与えることになるだろう。だからこそ、上司は「程度問題」である「べき論」の境界線を安定させなければならないのだ。
では、上司の「べき論の境界線」が「安定していない」状態とはどういうことか。ある日は9時5分の出社でも怒らないのに、別の日には8時55分に出社してきた部下に対して「ギリギリだろ、お前には社会人としての自覚がないのか!」と激高するようなケースだ。
上司が、日によって「べき論の境界線」の位置を動かしてしまうのは、「許すor許さないのスイッチ」や「怒るor怒らないのスイッチ」と密接に関係していて、「機嫌」や「相手によって」、そのスイッチが入ったりは入らなかったりするからではないだろうか?
機嫌の良い日は失敗を見過ごすし、機嫌の悪い日は些細なことにも突っ掛かる。また、機嫌だけでなく、相手によって怒る境界線を変える上司がいる。このときの境界線の正体は「ひいき」だ。Aさんには腫物に触るかのように接するのに、Bさんにはことあるごとにつらく当たる。機嫌やひいきで怒るパワハラ上司、ヒステリック上司が部下から信頼を得るのは難しいだろう。
上司は、「べき論の境界線」の位置を安定させたならば、その具体的な「位置情報」を部下に知らせておこう。上司は、普段から「ここまでは許す」、「ここからは許さない」というラインを明確にしておくのだ。会議の場、ときに飲み会で部下に話しておくのがよいだろう。
「許すor許さない」のラインは、機嫌やひいきでなく、大切な職場のルールや、相手の被った迷惑などを設定するのであり、部下が叱責を受けて当然のことを示しておくのだ。納得の伴う叱責ならば、部下は許容するものである。そして、上司自身も怒ったことで、後悔や自己嫌悪に陥ることはない。
その他、自分や他人が、普段どんな「べき」を大切にしているかを把握しておくと、どのような場面で怒りやすいタイプなのかがわかり、イラッとくるシーンが予測できるようになってくる。そのためには、「アンガーログ」という、怒りの日記をつけて自分の感情傾向を「文字化」することで客観視したり、「べきログ」という、自分がよく思う「~であるべき」を書き出して把握する方法などがある。
こうした地味な作業の繰り返しは、自分の怒りに関して重要な気づきを得る契機となる。目の前で起きたことが、たまたま自分の「べき論」と違うだけで短絡的な怒りを示すことが、単なるワガママに過ぎないと思い、またそのような怒りを恥ずかしく感じるようにもなる。詳しくは、拙著『パワハラ防止のための アンガーマネジメント入門』をご一読いただきたい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

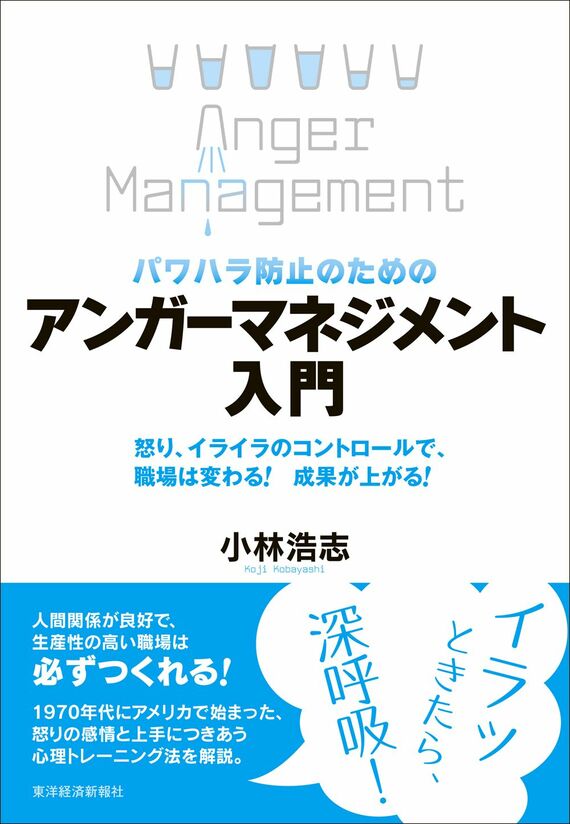
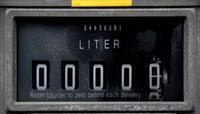





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら