結果オーライを引き寄せるのも政治の実力であり、それだけで非難されるべきものではない。危機の本来的性質上、予想外の事態に事前の計画や備えが無効化されることは珍しくない。しかし、場当たり的な判断には再現性が保証されず、常に危うさが伴う。
実際に、日本の第1波対応の舞台裏からは、多くの危うさや課題が浮かびあがった。
総力戦でやらざるを得なかった
パンデミックのような国家的危機への対応にあたっては、政府内はもちろん、官民の総力を挙げた対応が求められる。しかし多くの場合、政府部署間における情報共有への抵抗や組織の縦割りによる整合性に欠ける意志決定などの障害が立ちはだかり、効果的な危機対応体制の構築は容易ではない。
ある程度運用が定着した自然災害への対応と異なり、感染力や特性が不明な未知のウイルス対応という難題に対し、官邸は試行錯誤を重ねながら、あるべき司令塔機能の模索を続けた。「総力戦でやったし、やらざるをえなかった」と菅義偉官房長官は当時の危機感を振り返った。
初動において実質的な政策検討や意志決定の舞台となったのは「総理連絡会議」と呼ばれる首相を交えた非公式な会議体であった。1月23日の武漢封鎖の直後からほぼ連日のように開催されるようになり、総理執務室に各省幹部数十人がすし詰め状態で日々の状況把握と大方針の検討にあたった。情報伝達改装の低層化により、情報収集と意志決定の迅速化が図られる利点があったが、その裏返しとして当初は「生煮え」の案や不確実な情報が首相に披歴される危うさもあった。
1月下旬に武漢在留邦人をチャーター便で帰国させるオペレーションについては、総理室の主導の下で「事態室」と呼ばれる事態対処・危機管理担当の官房副長官補室が事務機能の中核を担った。
厚労省、外務省、国交省などの関係省庁と連携を取りつつ、民間航空会社や帰国者の受け入れ先ホテルなどに協力を要請し、官民協働体制の構築にあたった。しかし、未知の感染症への社会的不安から、隔離期間中の帰国者の対応にあたる事態室には過大な業務負荷がかかるなど準備期間の短さや体制面の課題も露呈した。
1月30日に閣議決定により内閣官房に新型コロナウイルス感染症対策本部が正式に設置された後、同対策本部の下に幹事会が設置され、ここが政府としての基本方針の策定等に向けて各省の政策連携の基盤となった。




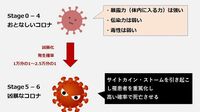


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら