JALがコロナ禍に切り開く「工場見学」の新潮流 2日で1万人参加「リモート工場見学」の魅力
株式会社JALエンジニアリング技術部技術企画室・谷内亨さんは、リモートの魅力を次のように話す。
「普段の工場見学では、参加者は安全面から機体の下に立ち入ることができません。そのため遠目からエンジンやタイヤをはじめとした細部を眺めるしかないのですが、リモート工場見学では整備士が近づくことで、通常の工場見学では見ることができない機体の一部を、映像でお届けすることができます。また、未就学生の子どもたちをはじめ、さまざまな理由で見学に来れない方がたくさんいます。そういう方々にもワクワクしていただきたいという思いがあるので、定期的にリモート工場見学を続けていくつもりです」
この日、リモートで子どもたちと参加したお父さんも、「小さな子どもがいるので、実際の社会科見学に行くことは難しい。ですが、こういった形であれば家族と一緒に見ることができ、2歳の息子もとても興味深く飛行機を見ていて、とてもよかったです」と大満足だ。
「リアル以上に負担が大きい」という課題も
一方、課題がないわけではない。実際の工場見学では参加者の年齢層などが見えるが、リモートではどんな層が参加しているのか把握しづらい。そのため、子どもに合わせて話すべきか、もう少し難しく説明して詳細が伝わるようにすべきか、といった点は悩みの種となる。
スタッフの数も、現場の映像班に加え、スイッチングなどを担当するスタジオ班を用意するなど大規模となり、手間と時間がかかる。また、JALのリモート工場見学では格納庫という特殊な環境下だったこともあり電波状況が安定せず、事前に撮影した「ホロレンズ2」の映像を組み合わせて進行するなど、リアル工場見学にはない労力が発生することも想定しておく必要がある。
それでも前出の山本さんは、「大手企業と垣根をこえて何か新しいことを生み出していくことが、働き方改革の文脈にあると思っています。日本社会の多様性のある働き方を実現させるということで、いろいろな取り組みを行っていきたい」と強調する。
















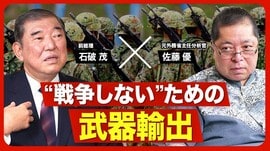














無料会員登録はこちら
ログインはこちら