人が生み出した「想像の共同体」国民国家の本質 「民主主義の知識」は今を生き抜く武器になる
そもそも選挙は、「より良い人」を選ぶための制度ではありません。100年以上前の話ですが、英国の名宰相、ウィンストン・チャーチルが、次のように明言しています。
「自分を含めて選挙に立候補するのは、目立ちたがり屋やお金儲けをしたい人など、ろくでもない人ばかりである」
「選挙というのは、こういった信用のおけない人たちの中から、相対的にマシな人を選ぶ忍耐のことである」
「したがって、民主政は最低の政治形態である。ただし、これまで試されてきた王政や貴族政など過去の政治制度を除けば」
こういうリアリズムが理解できれば、投票は簡単です。女性議員が少ないのなら、女性の候補者に投票すればいい。若い議員が少ないのなら、若い候補者に投票すればいい。
市民がすべきことは、忍耐を強いられながらも、「100%満足はできないけれど、他の候補者に比べれば、多少はマシ」な政治家を選ぶことです。これらのことがわかっていれば、「良い候補者がいない」からといって、白票を出したり、棄権したりするといった誤った結論には至らないのです。
政府と市民は、対立するものではありません。政府は市民がつくるものなので、今の政府が気に入らなければ、選挙に行って政府をゼロからつくり直せばいい。そして、新しいルールをつくればいい。政治を変えるのは自分たちの1票であることを小学校や中学校で教える必要があるのです。
今こそ必要になる「強い武器」
ところで、新型コロナウイルスでは世界の指導者がまったく同じ3つの課題に懸命に取り組んでいます。
その様子はSNSで世界に同時に発信されます。それを見ている市民の政治に対する関心は高まるのではないでしょうか。現に韓国では総選挙の投票率が10ポイント弱上がったと報道されています。パンデミックは投票率を上げるかもしれません。
人が生きていくためには、自分の頭で社会のあり方を考える力が非常に大切です。だからこそ学校の現場で子どもたちに、社会に出ればすぐにでも直面する基本的な問題に対する考え方や心構えを教えて、つまり、最低限の武器を与えて、リテラシーを育てていく必要があるのです。
強い武器を身につけ、そして武器の正しい使い方を教えられた子どもたちが、これからの世の中を変えていくのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

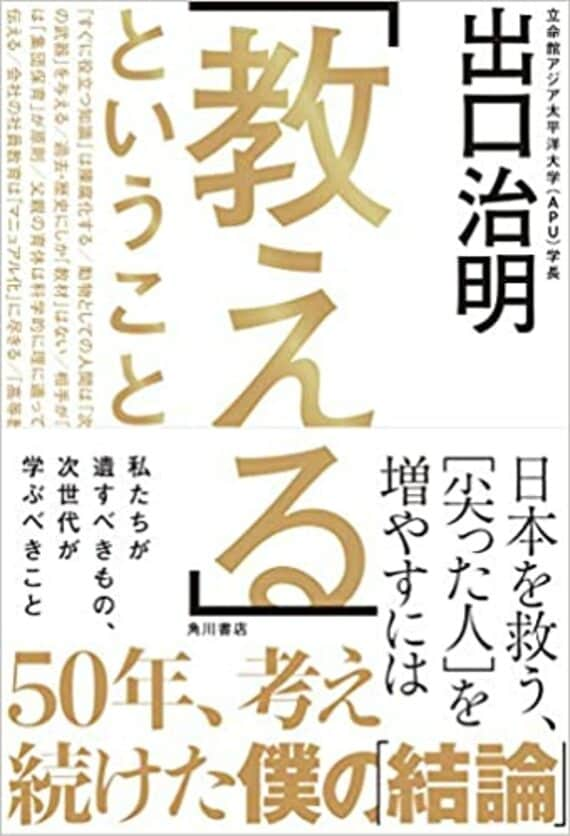































無料会員登録はこちら
ログインはこちら