パナソニックの中国傾注がどうにも心配な理由 コロナショックで前提は大きく変わっている
谷井昭雄(4代目)社長時代には、1990年にアメリカの映画メジャーのMCAを7800億円で買収したものの統治できず、5年後に株を売却して約1600億円の損失を出した。
森下洋一(5代目)社長は、薄型テレビが台頭してくるのには時間がかかる。まだまだブラウン管テレビの時代が続くと判断し、成熟製品に賭けた。この結果、液晶テレビ競争に乗り遅れてしまった。
中村邦夫社長(6代目)は、「打倒液晶」を掲げ、プラズマディスプレイパネル(PDP)事業に6000億円を投資する。ところが、液晶の台頭が読めなかった結果、撤退を余儀なくされた。
大坪文雄(7代目)社長は、2009年に4000億円以上を投じて三洋電機を買収。完全子会社化するための追加投資も含めて、最終的に8100億円以上も投じたが、円高ウォン安を背景に、韓国メーカーが猛攻勢をかけてきたことで三洋の主力製品だった民生用リチウムイオン電池の市場価格が2年で3割も下落した。その結果、2013年3月期決算で6000億円以上の評価損を計上した。
PDP撤退の判断を下した津賀一宏(8代目)現社長は、社長就任後に発表した中期戦略で「創業100周年となる2018年度までに、自動車関連事業で2兆円、家電を除く住宅関連事業で2兆円の売上高を目標とする」と表明したが、うまくいかず、戦略転換による再挑戦を強いられている。家電事業の中国への本格シフトはその目玉となる。
そのリスクは「計算できるか」
経営にはリスクがつきもの。言うまでもなく、リスクには2種類ある。カリキュレイテッド(計算できる)リスクとノン・カリキュレイテッド(計算できない)リスクである。経営者は、前者、後者ともに最大限の情報を収集して経営計画を立てるが、現実的には、リスクを極力計算できたと思っていても失敗することがある。ましてや、後者については、神のみぞ知る、と言っても過言ではない。
なぜか近年、「賢い(と言われている)経営者」の計算の誤りによる失敗が目立つ。その原因は、「賢い(と言われている)経営者」も「人」であるからだ。当たり前のことを言うようだが、次の真理がある。「人」は、自分が明日生きているか、死んでいるかさえも予測できない。
日本電産の創業者で会長兼CEOの永守重信氏にインタビューしたとき、「私は小心者だ。経営者は臆病であったほうがいい」と話していた。一見、歯に衣を着せぬ大胆な物言いと行動で注目される永守氏にして、こういった経営哲学を持っている。
日本電産も中国に入れ込んでいるが、永守氏はひやひやしながらリスクを計算しているのだろう。パナソニックも「中国における家電事業の成功」に賭けているが、再びPDPと同様、賭けが負けになってはいけない。中国に賭けていいのかどうか、戦略を練り直すという選択肢はないのか。津賀社長も社長である限り、強いリーダーシップを演じなくてはならないだろう。
だが、ときには、こっそりと臆病になっても悪くはない。臆病であることを自認し意思決定することは、「人は弱い存在である」という悟りであると同時に、リスクヘッジという論理的思考でもある。



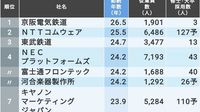






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら