50代で「うつになる人」「ならない人」決定的な差 残りの人生が「想定内な人」ほど要注意
その点、日本の武道は高齢になっても続けることができます。年寄りだからといって軽んじられることはありません。柔道でも剣道でも、段位が上の人は皆、ある程度年齢が高い人たちです。これは単に実力があるからといって昇段するわけではないという、認定システムに由来しています。
例えば剣道では初段が13歳以上であること、二段は初段受有後、1年以上修行を続けていること、三段は二段受有後、2年以上修行を続けていることというように、修行の必要年数が、段が上がるごとに1年ずつ増えていくのです。
六段から七段へは6年必要で、七段から八段へは10年の修行が必要。初段からの総必要修行年数は最低で31年もかかるのです。
武道は、単に競技の実力だけで段位が上がるわけではありません。ですからオリンピックなどの第一線で活躍する人たちの多くが四段とか五段くらいでしょう。年齢的にはそのあたりがピークなのですが、武道はそれだけを重んじるのではないということです。
大事なのは「勝つこと」ではない
長く続けた人、また年齢を重ね精神的にも円熟した人をリスペクトし評価するという基本姿勢が武道にはあるのです。単に力や技術だけでないということです。試合をして勝つほうが偉いとか上だとは考えていないことがポイントです。
人間、同じことをずっと長く続けているとどうしてもマンネリになり、飽きがきてしまいます。その点、日本の武道は長く続けることに重きを置いています。このような精神文化を背景にした武道を続けている人は、マンネリズムによって起こる精神の停滞を、おのずと寄せ付けません。うつになりにくい精神構造を身に付けていると言っていいと思います。
先ほどのアプリの話に当てはめると、スポーツ、とりわけ柔道や剣道などの武道を続けている人は、庭に大きな桜の木が植わっていて、満開の花を咲かせている状態だと考えられます。
あるクイズ番組で知ったのですが、桜の葉や花からはクマリンという物質が出ていて、それが周囲の雑草を駆除する作用があるというのです。大きな桜の木が1本生えていることで、おのずと「うつの雑草」が生えてこない。
武道を若い頃から続けているという人は、心の庭に大きな桜の木が立っているようなもの。自然と雑草が生えてこない精神環境を整えているわけです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

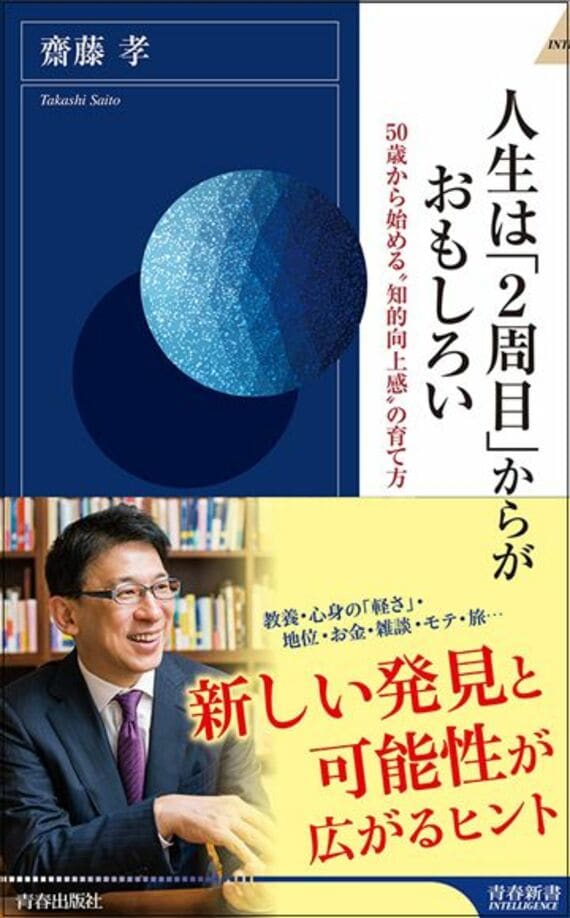






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら