
平成が終わり、新しい元号の時代となる。それに伴い、元号に関する話題が豊富だ。鉄道に関しても、平成駅(JR豊肥本線)、昭和駅(JR鶴見線)、大正駅(JR大阪環状線、島原鉄道など)といった元号と同じ名前の駅に注目が集まっている。
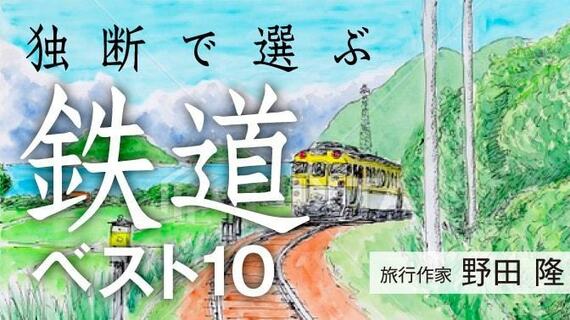
しかし、明治駅は存在せず、かろうじて明治神宮前駅があるだけであるし、その一代前の慶応駅もないことから、さらに時代をさかのぼる人は多くないようだ。
そこで、今回は、江戸時代以前の元号で駅名にもなっているものを探してみることにした。あくまで「話のネタ」であって、学術的な研究でもないので、直接元号とは結びつかないもの、たまたま過去の元号と漢字が同じものも含めて話題にしてみた。
親孝行息子に由来
<養老(奈良時代)=西暦717~724年>
三重県にある近鉄名古屋線の桑名駅と岐阜県のJR大垣駅を結ぶ養老鉄道(2007年以前は近鉄養老線)は、名瀑「養老の滝」のある養老郡養老町を通っていることから名付けられた。町にあるのが養老駅であり、その名の由来は「養老の滝」である。

奈良時代初期に、貧しいけれど親孝行な男性が山中で偶然見つけた滝の水を汲んで老父に届けたところ、それは酒であって、老父は若返って元気になったという。
この話が遠く都に伝えられ、時の元正天皇の耳にも届き、天皇はこの地に赴いた。そして親孝行の息子を称え、「老人を養う」ことから「養老の滝」と命名し、元号も養老と改めたと伝えられている。
親孝行息子は、ひょうたんに水を汲んで家に持ち帰ったという話から、町のシンボルはひょうたんであり、駅ホームにもたくさんのひょうたんが吊るされている。

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら