役員9人辞任で露呈した官民ファンドの矛盾 産業革新投資機構が離陸早々に「空中分解」
税金から成り立つ組織での適正な報酬はどの程度か、というのは重要な問いではある。ただし、今回の9人の辞任の本質は高額報酬への反発ではない。
辞任に際し5人の社外取締役が出した異例のコメントからもそれはうかがえる。「混乱の根本原因は、日本型の最終決定権者が不透明なボトムアップ意思決定プロセスにあった」(坂根氏)、「政府が『国民の相場観に合わない』という理由で、一度了解した報酬形態をひっくり返した」(星岳雄スタンフォード大学教授)。
近年、政府が主導する形で日本企業のガバナンス強化が進められてきた。経産省、さらに政府がガバナンス不全であることを露呈したことは大きな痛手だ。
問われる官民ファンドの意義
今回の混乱の論点はまだある。特に大きいのが官民ファンドのあるべき姿だ。

税金を使う以上、一定程度の政策目的を負う。JICにも産業の育成というミッションがあった。同時に、ファンドである以上はリターンも追求しなくてはならない。前者は官の色合いが強く、後者は民に任せて官は口を出さないほうがいい。
本誌の12月1日号で、JICの前身となる産業革新機構の9年間をデータと取材で振り返った。得られた結論は、ベンチャー投資を成功させるには官の干渉を極力減らすことだ。
実際、JICは個別案件に対する経産相への意見照会を必要としない形を採り、報酬もより成果主義を強めるという方向でスタートしたはずだ。
一方、民間色を強めれば強めるほど官民ファンドである必要性への疑問が膨らんでいく。その矛盾に押し潰された結果、JICは空中分解しようとしている。だから官民ファンドは不要だ、と言ってしまえれば簡単だが、事はそう単純ではない。
日本には有力なベンチャーが育っておらず、既存産業の再編も進んでいない。完全に民間に任せてうまくいっていればいいが、残念ながらそうではない。中国は言うに及ばず、米国でも国家による経済へのバックアップは強まっている。
日本でも官の役割はあるはずだが、高度成長期に成功した行政指導や補助金、税制優遇などはうまく機能しなくなって久しい。そうした中、投資=エクイティを通じた官民ファンドという手法の可能性はあった。
経産省内でも一部の官僚達はそのように考えた。官の関与と民の自由度の両立というナローパスを実現しようとしたのが、今回のJICのスキームだった。
しかし、最適解を見つけられないまま、官の関与を強化する方向へ逆戻りしようとしている。であるならば、やはり官民ファンドは不要ということだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



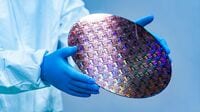





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら