
「紙中心」は入り口・出口双方で困難に
――新聞業界では紙の縮小が続き、朝日新聞の朝刊部数も10年前と比べ半分以下になりました。直近では、8月から土曜日の夕刊を休止すると発表しています。
私が取締役になってから大きな転換を進めてきた。精査すると直接お客様に届いていない新聞があり、実際にお金をいただくお客様を私たちの部数ととらえる「実売部数中心主義」に切り替えた(編集部注・新聞業界では、新聞社が販売店に卸しても実際の読者に配布されていない「残紙」が存在すると指摘されてきた)。
業界で先駆けて始めたから部数が急降下で目立ったが、いずれ通らなければいけない道だった。プリントメディア(紙の新聞事業)で「等身大の経営」を早くやるほかないと。

いくらよいコンテンツを作って紙に落としても、お届けされなければ何の価値もないし、配達網は現状かなり傷んでいる。新聞配達は(高齢化が進み)60歳以上の方々に配っていただいている。酷暑や休みの問題もあり、総合的に判断して、土曜日の夕刊をやめる決断を行った。
2022年2月のウクライナ戦争を機に、紙の供給の問題も急浮上してきた。原料である新聞用紙の生産が不安定になり、値上げを先駆けてやったが、三菱重工が(昨年6月に新聞紙の印刷に使う)輪転機をもう作らないと宣言した。「紙中心」を懸命に維持・向上させようと思っても、入り口と出口の双方で周囲の環境が許さなくなりつつある。


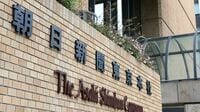
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら