「発達障害の子」に悩む親が知りたい超基本 「ぐずる」「こだわる」「怠ける」も症状のひとつ
近年、発達障害の診断基準が変わったこともあり、医療現場において、発達障害の考え方に変化がありました。
以前は、「多動があったら発達障害と診断する」など、特性にひも付けて発達障害の診断や症状の重さの区別がされていましたが、ここ数年は「どれくらい日常生活で困っているか」「どれくらい社会生活に適応できていないのか」という点に、重きを置いて診断が下されるようになったのです。“社会生活に適応できていない部分があって、日常生活で困っているなら、その場合は診断をつけましょう”そういう流れになっています。
診断基準の話からもわかるように、「発達障害とグレーゾーンの境界線」、また、「グレーゾーンと定型発達(健常者)の境界線」はあいまいです。だからこそ、子どもと向き合う両親や周りの人が「育てにくい」と感じることがあったら、問題を先送りにせず、困りごとを減らすように動くのが大切。
多少乱暴な言い方になりますが、その困りごとを発達障害の特性として受け止めても、子どもの個性として受け止めてもいいのです。そして、困りごとを解消するために使える手段があるのなら、できるだけ積極的に使ってください。特に公的な支援は一定の年齢までしか用意されていないことが多いので、受けられる内に受けたほうがいいとも思います。
「診断がついていないから」といって何もしないのではなく、今、子どものことで困っていることがあるのであれば、どんなことに手を焼いているか、不安に感じているか、その感覚を大事にし、それを解決していくことに力を注ぎましょう。
発達障害が完治することはない
発達障害はウイルスによる風邪や病気とは違い、もともとの脳の特性による部分が大きいため、基本的には完治しません。
しかし、程度に差はあるものの、ヒトの赤ちゃんはみな、脳が未完成な状態で生まれ、「目に入るもの」「聞こえてくるもの」「周りにあるもの」など、自分の中に入ってくる情報を栄養にして、少しずつ脳を成長させていきます。
発達障害の子の場合は、脳の中に発達しにくいところがありますが、脳の成長が環境によりどんどん促されていくことには変わりありません。だからこそ、両親が子どもへの接し方を変えたり、子どものために環境を変えることで、それらの刺激をもとに、子どもの脳を育てることはできます。
子どもの発達を促すのに、最も効果的なのは「親子のコミュニケーション」を充実させることです。発達障害は完治しませんが、脳科学の視点からいえば、発達障害の子も接し方次第で十分に伸びる可能性があります。そのためにも何か気になることや不安があれば、できるだけ早めに対応をしてほしいと、切に思っています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

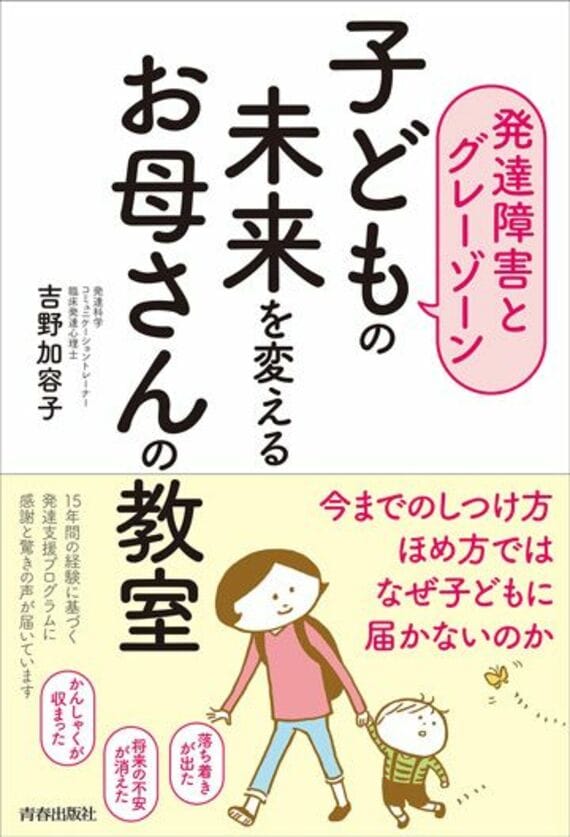































無料会員登録はこちら
ログインはこちら