幕末・維新を生きのびた、日本橋の大店たち 榮太樓、西川、柳屋・・・試練を乗り切った老舗

幕末、幕府の統制が揺らぐと江戸の治安は悪化。ある日、日本橋西河岸の榮太樓の店に、京都・大覚寺の寺侍を名乗る数人の武士が訪れ、「誰の許しを得て『榮太樓』を名乗っているのか。『樓』は高貴な文字だ」と脅した。こんな謂われのないゆすりが横行し、群衆が大店に暴れ込んでの略奪や打ち毀(こわ)しも相次いだ。彼らは「天狗がやった、やったのは天狗だ」とうそぶいたという。今に続く老舗は、存亡をかけた試練をどうやって乗り切ったのか。
業態を華麗に変更した「ふとんの西川」
日本橋の南側、日本橋通りをはさんでの通1丁目は「間口一間値千両」と言われた江戸第一級の商業地で、近江商人の店が集中した。豊臣の楽市楽座政策を機に、近江商人は全国に活躍の場を求め、御朱印貿易にも携わった。
今でも近江八幡や五個荘(ごかしょう)など北国街道沿いの街並みを歩くと、他の地方には見られぬ「勢い」が感じられる。
橋を渡ってすぐの「西川」は「近江八幡の御三家」、初代西川仁右衛門(にえもん)が元和元(1615)年、畳表や蚊帳を商う近江本店の支店として設けた。江戸はまだ普請中、畳表は江戸城や武家屋敷からの引き合いが多く、町屋向けに手代が売り歩いた蚊帳への需要も、江戸の街と一緒に膨張し続ける。売上は右肩上がりだった。
西川は経営の近代化に熱心だった。売上から運転資金、原材料費、当時多かった大火などの損失引当金を引いた分を従業員に分配する「三ツ割銀制度」は現代の会計理論にも通じ、寛文7(1667)年の勘定帳は、わが国に残る最古の帳簿とされる。「近江八幡の本家で拝見しました」と日本橋西川の店長・執行役員の伊藤敦司さんは語る。売り手、買い手、世間の「三方よし」とともに、近江商人の先進性と精神を現代の社員たちに伝える存在だ。

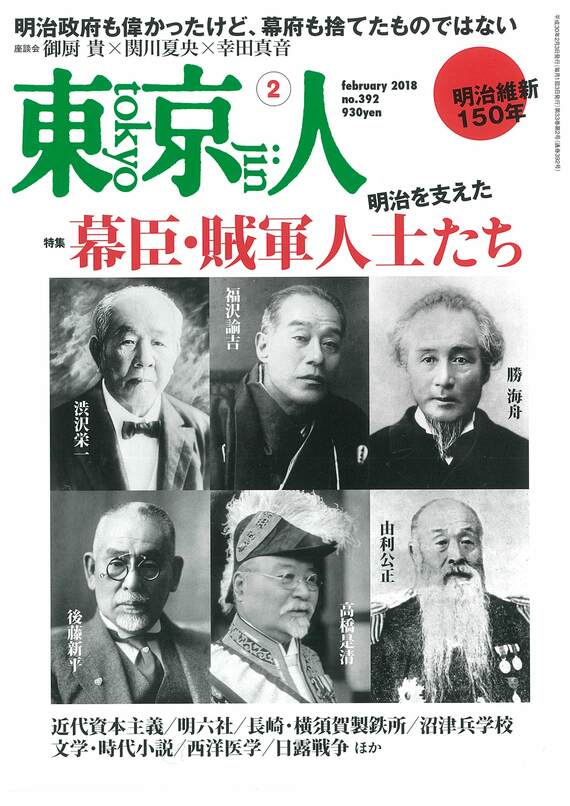






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら