
ブータンと中国、インドが国境を接するドクラム高地で、インドと中国の軍隊がにらみ合いの膠着状態に陥ってから約1カ月になる。この種の対立としては、1962年の中印国境紛争以来、最長のものだ。
中国国防省の呉謙報道官は、インドが惨敗を喫した1962年の国境紛争をあからさまに引き合いに出し、「歴史の教訓に学ぶべきだ」とインドに警告した。だが、歴史の教訓は、それを引き合いに出す側の都合に合わせられることが多い。
国際関係における「屈辱」とは
1962年の紛争は、高慢なインドが中国の要求をのまなかった代償であるというのが、中国指導部の見方だ。だが、インドにしてみれば、これは半世紀以上にわたって国を苦しめてきた屈辱にほかならない。
国際関係において「屈辱」とは、他国の名誉を傷つけ、地位を得ようとする試みを否定することであり、明白なヒエラルキーの構築を意味する。戦争は、相手に屈辱を与える格好のチャンスである。
屈辱が持つ、こうしたインパクトを理解している国があるとすれば、それは中国だ。中国国防省がインドに警告を発していた頃、習近平国家主席は香港返還20周年を祝う式典で、こう言った。英国が1842年に香港を収奪したことによって中国が受けた「屈辱と哀しみ」は、香港が中国に返還されたことで終わったのだ、と。
ナショナリズムをあおるために「屈辱の世紀」という言葉を広く利用してきたのが中国だ。1949年の中華人民共和国樹立により、「屈辱の世紀」は終わったことになっているが、東アジアの大国としての中国の自己イメージはその後、何度も打ち砕かれてきた。とりわけ、戦後日本の高度成長によって受けたショックは大きかった。

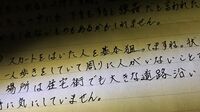































無料会員登録はこちら
ログインはこちら