「離婚しても子に会いたい親」が抱える焦燥 わが子を「連れ去られた」側が感じていること
一方、支援する側の人たちについてはどうだろうか。
「離婚の渦中においてかかわる機会の多い司法や行政機関は、離婚ありきで係争のノウハウを伝えるのではなく、たとえ離婚しても親同士であることは変わらないことや、冷静に歩み寄ることが必要だという心持ちの面も伝えていく必要があります。夫婦間の問題はしゃくし定規に決められるものではないし、向き合わず逃げっぱなしでは根本的な解決になりませんから。私自身は親同士の心の架け橋をモットーに活動をしています。そうすれば円満離婚ないしは修復だってありえますし、離婚後も親子関係が良好に築かれていくと確信しています」
なぜ「子どもを会わせない」のか?
面会交流についてどう考えたらいいのだろうか。
「同居親側が面会交流をさせない理由は、2パターンが考えられます。相手を喜ばせたくない、子どもがなついてしまうのが嫌だ、子どもに悪口を吹き込まれるか心配、相手が子どもを甘やかしてしつけが悪くなる心配、といった理由から面会交流に消極的なパターン。もうひとつは、面会交流するつもりはあっても、相手と連絡を取り合わなくてはならないことがストレスで、面会交流に後ろ向きになるパターンです。
同居親は相手から一時的に距離を置くこともいいけれど、最終的にはちゃんと向き合って子どもの養育のことを決めるという、親としての責務があると思います。それに面会には責務とは逆に行うことでのメリットも多いですので、行うことを勧めます。私のケースですと、離婚して1年ぐらい経って面会を始めたところ、息子も含めた3人の関係が瞬く間によくなりました。相手に預けている間、自由な時間ができるようになったり、感情的にならず相手を思い合える関係になれたりしたんです。そうして、精神的な安定を得ることができました。これは相手だけではなく自分自身も心持ちを変えたことによる結果です。
今後、子どもが大人になっていくに伴い父親からだからこそ学べることもあると思うので、父親と接する機会はすごく大事だと思います。それにもし相手に会わせずに悪口ばかり言って育てたとしたら、子どもが大きくなったときに“お母さんひどいよね”と、軽蔑されるようになってしまうリスクもあると思います」
相手の声に耳を傾けず、わだかまりを抱えたまま、年月を重ねるのはむなしいことだ。可能ならば、お互いに歩み寄る努力をしたほうがいい。それが2人のためになるし、何より子どものためになる。
(取材協力:高橋ユキ)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

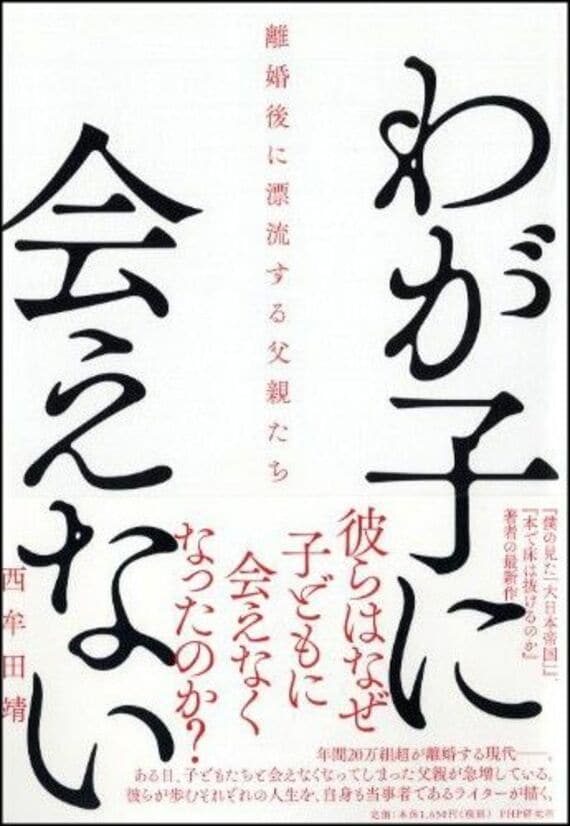






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら